虚ろな未来へ・4

天気は崩れていたが、然程寒さは感じなかった。
無論、暑くも無い。
肌に優しい温度――、生憎の雨模様にも関わらず不快な湿気も無く、ただ考え込んでいるだけでは、日常の疲れと規則的な雨音も相まって、ついついまどろんでしまいそうだった。
(…むかし…、昔なぁ――。正直、俺がアイツの事が気になり始めたのは、再会してからだし…な)
ファブレ公爵家へ下男を装って潜入した当時は、ルーク・フォン・ファブレは復讐の為の目標物(ターゲット)にしか過ぎなかった。好意と呼ばれるような感情は一切無く、最大の仇敵であるファブレ公爵の親族――、妻と幼い子どもの残酷な殺戮方法だけを考えていたはずだ。
(……まぁ、実際に実行する前にアイツはすり替えられちまったわけだが)
結果論ではあるが、ヴァンが摩り替えていなければ今頃『ルーク』を殺していたかもしれない。無論、始祖ユリアの預言に縛られる限り有り得ない未来なのだろうが、少なくとも今と同じ感情を抱く事だけは無かっただろう。それだけは断言出来る。
「…もしかして、すり替えられてから逢ってたりするのか…?」
ヴァンの監視下に置かれていたアッシュが簡単にバチカルへ近づけたとは考えにくい、もし機会があるとすれば一度、二度程度の話なのだろう。赤毛自体がオールドラントにおいてある程度の希少価値ではあるから、記憶を慎重に辿れば何か糸口が見つけ出せるかもしれないが。
「……うーん。」
顎に右手を添えて考え込むが、あんな見事な赤毛を余所で見かけた事など――、…… 。
(……あ、れ。ちょっと待て。 今 … 、何か…)
余所――、王都バチカル以外と考えるから思い当たらないのでは、と視点を変えてみる。
行方不明事件後の『ルーク』の世話係兼護衛役に任命されてからは、殆どの時間を屋敷で過ごしている。せいぜい、お遣いか剣の稽古の為に城下へ降りる程度だ。無論、何処ぞの王族の子のように軟禁されていたわけでは無いから、お勤めに支障をきたさなければ基本的に何処へ行くも自由の身ではあったのだが。
「… 逢って、 る?」
雨、灰色にくすむ天からは――、しとしとしとしと、降り続く雨。
焦点の合わない思い出の輪郭を必死で辿って確かめようとするのに、それは途切れ千々れ、もどかしい程に思い通りにはならない。
「…アッシュ……」
恋と呼ぶには些か身勝手で傲慢な――、感情の強さ。
幼馴染としてなら嫌悪されていない自信はあったが、性への欲求が伴う深さとなれば、流石に否定の可能性で考えていた。けれど…――。
「…堪え性が無いんだよなぁ」
今、確かに掌の中に在る『幸福』は、前触れも無く現れる狂気に容易く蹂躙され簒奪者の靴裏で踏みつけられ、粉々に砕けてしまう事を知っている。いいや、思い知らされた。眼前にした惨劇は幼い記憶には重すぎて、今でもハッキリとは思い出せない。だけど、鮮烈な赤だけは覚えている。
(……不安が…、消えない。
幾ら拭っても、恐怖が消えない――…)
それは目の前で数多くの同胞を、幸せの象徴である家族を、故郷を、全てを失った過去からじわりと浸み出してくる闇のようなものだった。今、如何に充たされていても決して心が安堵感に包まれる事は無い。心的外傷から来るものだと言う自覚はあるが、治療しようという気も、治癒するとも考えられない。慢性的な病と同じ、持病のようなもので、幾ら程続くかも知れない人生の中で気長に付き合うしかないだろうと既に達観してしまっている。
「…自分の事でいっぱいいっぱいで、見っとも無くがっつくなんて、情けない」
なかなか波乱万丈な人生を送ってきただけに、大佐程では無いにしろ、自制心には自負がある。何が起こっても動じない――とまではいかないが、頭の切り替えは早い方だ。有事の判断・決断力もそれなりに優れているはずだ。それなのに、今回の件だけはどうにも――… 抑えが利かない。
ヴォォォォ ……
(…俺とヴァンの関係をファブレ公爵に勘付かれる訳にはいかなかったから、私的な接触は殆どしてない。なら…、 やっぱりバチカルで、 だよな。他の場所で逢ってたとは考えられない)
ヴォァァ…… グァォォ …
(けど――、何時……? 逆に、六神将として頭角を現してからは自由に動けないよな。顔が知れてるだろうし、神託の盾(オラクル)騎士団の任務だってあるだろ)
ガァ…… グアァ 、 ゴゥヴァァ……
(なら、もっと小さな頃か? …そう、だな。アイツは昔から優秀だったから、子どもだったとしても、寧ろそれを武器にして巧く逃げ出せる、か)
ウゴォォォァァァ……
「だぁぁぁあああああ!! ウルサイ!! なんなんだ、さっきから、ゴァゴァガァガァ!!」
先程から遠く近く響き渡る風の唸り声のようなそれに思考を邪魔され、若干八当たり気味にガイは両手を振りまわして大声をあげた。
「ったく、何の音だ――、ッ…」
静かに泣き濡れていた空だったが急激に天候が変化したのかと、金髪の護衛剣士は多少手狭な洞窟の入り口を見遣り、見慣れぬ光景に息を呑んだ。――…幾ら荒事に慣れていると言っても『コレ』は、無理だ。全面降伏しても致しかない。いや、死霊使いの異名を冠する約一名だけは常人とは異なる反応をしてくれそうだが、この珍現象を前にして奇人変人を引き合いに出すのは愚の骨頂だろう。
(…本気で勘弁してくれ…)
幸い『彼ら』は此方には微塵の興味も抱かずに、不安定に揺れながら、列を成して真っすぐ谷の奥へと進んでいた。その有様を現世にあるものに置き換えるなら、夢遊病患者が最も近いか。意識も無く、ただふらふらと彷徨い歩く様は異様の一言に尽きる。
(……ひと…、じゃないよな。どう考えても)
当然だ。世界にふたつしか存在しない飛晃艇を駆って漸く辿りつける未開の地に、一般人がおいそれと立ち入れる道理が無い。低く、遠く、うねる声は明確な意図も最早存在していないのだろう。彼らは軍服を身につけた者が多いようだったが、中には女性や小さな子どもいた。落ち着いて様子を観察してみると、気狂いのような雄叫びを上げるそれもあれば、静かに歩を進める者もいる。最初は現世へ無念を残した亡者の群れかと悪寒を覚えたが、そう短絡的に考えるものでは無いようだ。
(…さっきの殺気みたいなものが急に消えたのは…、
もしかして、こういう奴らが出てくる領域だから怯えて逃げたのかもな。
――…気持は分かる。俺も逃げたいぞー、猛烈に)
無論の事、惚れた相手を残して一人帰艦するなど言外なので、行動には移さず希望として心に思い浮かべるだけではあるが。
(……しかし、本当に何でこんなものが…)
取り合えずの危険は無いと判断すると、片膝立ちの半端な姿勢で固まっていた悲劇のホド出生である青年は、気配を乱さぬように、ひとつ息を吐く。そろそろと剣と荷物を傍へ引き寄せ、何時でも応戦可能なように、体勢を整えて得体の知れない『モノ』達の行進に視線を戻す。
「そう、警戒しなくても大丈夫だぜ。アイツ等は只の浮遊思念体だ」
――…!!
突如として背後に湧いた気配、気易く掛けられた声に一瞬で総毛立ち、ガイは瞬時に身を翻した。緊張の場にあって、これだけの体裁きが可能であるのは流石の一言だ。
「よッ。…って。…なんだ、けっこー色男だな?」
振り向いた先にはノンビリを軽口を叩く――…見事な赤毛の青年が、座って、いた。
全く以て緊張感を欠如させた立ち振る舞いに、つい気が削がれて構えに迷いが生じるガイだ。
「…何者だ」
背中まで届く緩やかな曲線の赤毛――…、アッシュやルークのそれは譜言に詠まれる聖なる焔の輝きであるが、目の前の派手な気配の青年のそれは、享楽に咲き綻ぶ艶華の芳香を纏い、ふわりと揺れ、他人の闇を見透かすような美しい藍菫の瞳は、愉快そうに瞬いている。
「同じ事、俺もアンタにききたいんだけどねー?
俺様は、ゼロス・ワイルダー。テセアラの神子様よ?」
「…テセアラの、 神子?」
聞き覚えのない地名だと、金髪の剣士は不審そうに言葉を繰り返す。趣味と実益を兼ねた卓上旅行のお陰で世界の地理には詳しい。辺境地独特の文化にもそれなりに精通しているはずだが、思い起こす限り、男子を神の子として祀る国も地域も存在しない――…はずだ。
「…知らないな」
「おーい、おいおい。俺様を知らないなんて、何処のド田舎からでてきたわけ?」
大袈裟な振る舞いで頭を振り、芝居掛かった口調で嘆く鮮やかな華のような青年は――あくまで本人の弁ではあるが――どうやら相当の有名人らしく、此方の無知を責め立てる態度だ。
「……と言われても知らないものは知らないしな…。
神子、って事は…、ローレライ教団関係か?」
オールドラントに於ける信仰の対象は、ローレライ教団のみである。生という交響曲(シンフォニア)を己が魂で奏で続ける人々にとって、未来へ続く譜面を謳い上げてくれる教団の存在は唯一絶対の拠り所だ。無論、依存度の個人差はあるが、教団や始祖ユリアを否定する者は皆無だ。
――…いや、正確には『皆無だった』と、過去形にすべきだろう。
偉大なる始祖ユリアが施した、人の子の幼くか弱き力では決して抗えぬ預言という呪縛を、無数の代償(いたみ)を伴いながらも、必死で振り払おうとする愚かしくも愛しい存在を知るのだから。
「あん? ローレライ教団? 何? 俺様に断り無く勝手に信仰団体作っちゃってるの?」
「…? 何を言ってるんだ。教団は昔からあるだろ… う …… ?」
言い掛けた言葉が途中で詰まる。澄み切った大気のような空色の瞳が、ある一点を凝視しており、視線の先を辿った華やぐ紅髪の青年は、うん? と、何処か可愛らしく小首を傾げて見せた。
「どーしたい、兄さん? エクスフィアなんざ、そんな珍しいモノでもないだろ」
指し示す胸元に――美しい石榴の輝石――エクスフィア、と言うらしいが、それが直接肌へと埋め込まれている様子に言葉を失っていたガイだが、事も無げに返される姿に緊張を解く。世界は広い。己の知識の外で様々な技術や文化、慣習が存在していたとしても、不思議では無いからだ。
「ガイ」
「ん?」
「ガイ・セシル。俺の名前ですよ。神子様? マルクト帝国の城の下働きをさせてもらってる」
「ふーん? アンタ、下男って感じしっないけどねー?
マルクトってのも聞いたことねぇ名前だな…。
嘆きの残骸(レイド)がウロウロしてる境界だし、別次元へ飛ばされてンのかなー…。
参ったなー、ハニーともはぐれるし。あー、怒ってるんだろうなぁ、ロイド君」
最初は探りを入れるような口調であったものが、段々と自身の内へ向けたものへと摩り替り、仕舞には頭を抱えてしゃがみ込んでしまう軽薄な容姿の神子へ、下働きと名乗った金髪の青年は完全に毒気を抜かれて、いっそ気遣う様子で相手を見遣った。
「えーっと…? その、…ハニー…? ロイド? ってのは、連れか何かか?」
「まぁねー、一緒に旅をしてるんだけど…」
「二人で?」
「あー、今は二人かな。そっちは? こんな境目でなにしちゃってるわけ?
確かに連中は直接危害を加えてくる事は無いけど、奴らの近くにいると生気を奪われて衰弱するぜ。まー、アンタみたいな立派な成人男子なら少しの時間でどうこうなんてないけど、こんな場所に長居しない方がいいんじゃないの?」
――…境目、境界、別次元。
朱牡丹の如く華やぎを魅せながらも、翳りを帯びた彼岸の彩の麗しき面立ちの神子の言葉は深く謎めいて、ガイは戸惑いを隠せない。
「…俺も連れがいてね。そいつの帰りを待ってるから、ここにいなきゃいけないんだ。
それより、さっきから気になってるんだが――…、境界とかなんとか…、何の事だ?」
「あー、まぁまぁ、いいじゃん。そんな細かい事気にしなーい、ってな。
しかし、こんないわくつきの場所に何の用なんだか。アンタの連れってな、相当モノ好きだな」
「そーゆー神子様こそ、連れとはぐれて迷子みたいですけど?」
歯に衣着せぬ物言いは好ましいが、余りの厚顔ぶりに温和な常識人である金の髪の青年も、流石に苦笑を浮かべて、意趣返しとばかりに冗談を交えた。
「あははー、まーね? あー、どーしよっかなー」
岩壁に背中を預け、膝を立て頬づえをつく様子は、軽薄そうな口調とは裏腹に、虚無と寂寥を美しい瞳の中に滲ませており、基本的に世話焼きでお人好しな性格のホド出自の青年は、つい口を挟んでしまう。
「何処ではぐれたんだ? 俺で良ければ、一緒にさがしましょーか?」
「……あ、そーゆーわけじゃなくって…。てか、お兄さん相当お人好しだしょ」
「よく言われるよ」
体裁を取り繕って明るく笑って見せる姿に、痛ましさすら感じて、ガイは軽く肩を竦める。難しい相手だ。この短い遣り取りの間で正しく相手の特性を理解して、距離を取り直す。踏み込み過ぎればかわされる。逃げを打てば、諦観の視点を持たれる。そう、これは――敵の多い人間の処世術だ。
「…それで、連れの件はいいのか?」
「ああ、サンキュー。でも、問題ねーから。
多分だけど、俺はここの人間じゃないから、あんま動かねー方がいいんだよ。
ウロチョロしてっと、戻れなくなる可能性があるし」
「………」
気に掛かる単語は幾つも存在していたが、気遣いの心が人一倍備わっている苦労人の剣士は、敢えてそれらを聞き流し、それと無く話題を逸らした。
「にしても、アイツらは何だ?
お前さんは分け知りみたいだが…」
洞窟の入り口から窺える霧雨にけぶる異常は先程から一切変わり映えも無く、混沌の気配にガイは軽く頭を押さえてみせた。オールドラントでは亡くなった人の魂は安寧と共に惑星を巡る生命環に還るというのが定説となっている。『これ』がそうというのだろうか――…しかし、それにしては……、
「生々しいだろ。あの連中」
「………え、」
まるで心を読んだかのような絶妙なタイミングで声を掛けられ、一瞬対処が遅れる好青年然とした金髪美形の剣士の反応を、朱牡丹を想わせる艶やかな神子は面白がるように妖しく微笑んだ。
「嘆きの残骸(レイド)――…、ってもわかんねーか。
つまり、人から湧き出した負の感情の塊がアイツ等だ」
「…感情? 魂とは違うのか?」
聞きなれない単語に戸惑いながらも冷静に疑問を口にする護衛騎士の様子に、頭の回転はそこそこ良さそうだと、その力量に満足するテセアラの神子である。愚鈍な人間と会話を成立させるのは、なかなかに忍耐が必要だ。今は、残念ながらそういった余裕が無い。
「ああ、違うな。あくまで『感情』の部分だ。それも、負の方向に偏った、な。
人間、生きてれば怒ったり笑ったりする。その感情ってのは、大概は噴出した本人の魂の中に収まるんだが――、一部の感情は元へ戻れなくなる。どうしてか分かるか?」
「……いや…」
残念ながら憶測を推測へ昇華出来る程の確証が得らない。挑みかかる享楽的な視線に柔らかな苦笑を浮かべながら、ガイはゆっくりと首を横にした。
「ンだ、つまんねーな。外れてもいいから、何でも言ってみろよ」
「…。なら言うけど、還る場所が無くなった。その…当人が亡くなった、とかか?」
「ピンッポーン♪ ご名察。ンだ、けっこー使えるみたいだな。アンタ」
「…お褒めに預かり光栄ですよ。神子様」
軽く肩を竦めて称賛を聞き流し、再びガイは洞窟の外に広がる異様な光景を見遣る。敵意も悪意も感じられない。ただ――、恐ろしくて、悲しくて、辛くて、そして寂しい。非業の最期を遂げたであろう人々の報われない感情の断片が覗えて、そっと空色の瞳を伏せた。
「あんまりジロジロ見ないほーが賢明だぜー? 連中は戻るべき感情の器を求めて彷徨ってる。うっかり目ェ合わせて同調した日にゃ、エライ事になるぜ」
「……エライ事って具体的には?」
赤毛の神子の忠告を素直に聞き入れて、ガイは物悲しく蠢く嘆きの残骸(アシュットレイド)へ背を向け声の主へと向き合う態勢を選ぶ。直接的な被害が無いのであれば、意識から遠ざけて遣り過ごすのが最善だろう。
「んー? どうってそりゃアレよ。心を喰われる」
「……? って、どうなるんだ? 」
顎に指を掛ける件のポースでガイは首を捻った。オールドラント全土に影響力を及ぼすローレライ教団は過去の先人を敬うというよりも、預言により今を生きる人々を導びく意味合いで成立する団体である為、始祖ユリアが提唱した大地の上で愚者の舞台を踊る第二世代の人々は一律に、心霊や超常現象に縁が薄いという背景を持つ。
「そんな軽くで済めば儲けものだぜ? ヘタすりゃ廃人。心を喰われるって事はそーゆー事」
「…はー、そりゃ願い下げだな。俺はまだ、そういうのは困るし」
「ん? ナニナニ? 若しかして、アンタの連れってコレ?」
道化染みた口調で肩を竦めてみせる好青年然とした金髪の剣士へ、享楽的で世俗的な――大凡『神子』らしくない雰囲気の御使いは、白々しいまでの陽気さで興味津々と小指を立てて、野次馬根性丸出しに窺って見せた。その下世話な仕草は到底神へ属する類の人間のそれでは無いが、妙にしっくりとくる。しかし決して彼自身の品を損なう事は無く、不思議な魅力の神子様だと、ガイは溜息を吐く。
「…残念ながら違いますよ。今のとこはね」
「ってコトは片思いかー。まー、俺様には遠く及ばないけど、それなりにイイ線いってるのに、モテないなんて、ホント残念だなー」
「余計な世話ですよ。それより…、えと、ゼロスだったよな?」
「ああ、ゼロス・ワイルダーだ。ゼロスさまーって呼んでもらってけっこーよ?」
「……そう呼ばなきゃダメってんなら呼びますけどね」
『神子』の肩書と気品を漂わせる立ち振る舞いから、ゼロスと名乗った人物がそれなりの身分の者だと、持ち前のカンでとうに察していた人当たりの良い青年は、微苦笑を浮かべながらも、素直な姿勢で応じた。十年の歳月を公爵家の子爵様に仕えて過ごしただけあり、高貴な血筋の生まれとやらをあしらう術には長けており、余裕さえ感じられる態度は流石の一言に尽きる。
「うわ、つまんない反応。そこは、がーって怒るとこっしょ?
まー、いいけどな。ゼロスでいいぜ。ガイ?」
「ああ、よろしく。ゼロス。――…それで、あんなのが湧いてるけど、アンタの連れの心配は要らないのか?」
常に周囲への配慮を忘れない青年は、流石の惨状に肩を竦めて尋ねる。無論、本当に問題があれば目の前の人物が如何な大物だろうと、流石に慌てて見せるだろうと予想するだけに、本気の心配では無く、あくまで形式的な言葉ではあったが。
「ん、まーね。ロイド君なら平気っしょ。それより、何時までも出口にぼーっとしてないで、コッチに座れば? 俺様薄着だから、ちーっと寒くてさ。本当はかわゆーいハニーがいいんだけど、仕方無いから野郎の湯たんぽで我慢してやるよ」
言われてみれば緩やかな長髪を背中に流す神子様は随分と軽装だった。黒のタンクトップに肩を大きく出したロングジャケットは華やか容姿に相応しい可憐な色で、胸元のエクスフィアが冷たく輝くのが再び目に留まる。手元の剣は鞘に収まったまま無造作に放り出され、全く敵意の欠片も感じられない。そんな神子様の様子に、真面目に警戒し続けるのがバカバカしくなったガイは、ゆっくりと近づいて直ぐ隣に腰を落とした。
「…なぁ、『それ』って何なんだ?」
「ん? そういやさっきも不思議そうにしてたけど、ホントに知らないワケ?」
「ああ。知らないな」
「ふーん…」
意味深な様子で小さく息をつき、ゼロスは億劫そうに説明する。
「これは『エクスフィア』つって、パッと見は宝石みたいだけど、タダの飾りじゃないぜ。人体へ直接装着する事で使用者の能力強化を担ってんの。ま、俺様のはちっと特別だけど?」
得意気に微笑む姿が酷く堂に入っており、一瞬見惚れてしまう程だ。自信家具合に厭味さは全く感じられず、寧ろ心地良い。随分とカリスマ性の高い神子様だと、ガイは半分呆れ気味に話に耳を傾けた。
「そりゃ凄いな。装着って事は外せるのか?」
「まーな。けど、手順を踏まないと駄目だから今やってみせるのは無理な」
「へぇ…」
少しばかり残念な気がするが、仕方無いとガイは不思議な輝石から視線を外した。肉体強化を図る技術はこのオールドラントには――…自身が知り得る限りでは存在しない。未知の知識への興味は尽きないが、正直、今はそれ所では無かった。ファブレ公爵家の子爵の世話係兼護衛役という長年の責から、苦労性に育った青年は思いがけずに低い岩肌の天井を仰いだ。
「…はー…」
右隣には茜色のふわふわとした緩い波様を描く美しい髪が、無防備に揺れており、今まさに心を占める愛すべき人の姿を連想させた。ついつい手を伸ばして、滑らかな感触を指先で確かめる。捕らえどころ無く指先から掌から零れ落ちてゆく『赤』はとても美しかった。
「……えー…、あのー。兄さん、何してんの?」
「うん…?」
怪訝そうな声にも生返事を促されるだけで、今ひとつ正気に戻らぬ様子の正統派美形の剣士に、享楽と快楽を愛する麗しの神子は困り果てる。野郎に髪を少しばかり触られた位で大騒ぎするのも、同じ男として甚だ疑問なところではあるが、このまま自由にさせているのも女好きの沽券にかかわる由々しき事態だ。
「なに、コッチでは赤毛がめずらしーわけ?」
「ん? …ああ、そう …だな。
アイツの髪はもう少し深い色かな…、ここじゃ暗くてよく分からないけど。
ルークのはもう少し明るいイメージがあるんだが…。
けど、この色も綺麗だな。……うん、綺麗だ」
「…っ、そりゃどーも」
第三者からすればどうにも奇妙な構図だ。自身でも恵まれていると自負するだけに、容姿への賛辞は聞き慣れているが、それでも政治的な背景や色を含まない純真な賛辞は嬉しいもので、妙に照れてしまう。そんならしくない自身の反応への戸惑いと気恥しさから、ゼロスは清廉潔白そうな正統派美形剣士へおざなりな返事をして、ふいっと横を向いて見せた。
そんなテセアラの極楽トンボなお気楽神子にしては、随分と珍しく初々しい反応に露とも気付かずに、ガイは美しい髪を指先で梳きながら、思索へ耽る。
(……あか い、 髪。
確か、何処かで…。そうなんだよな…、オールドラントじゃ赤毛は珍しい。
うーん…、思い出しそうな気がするんだけど。
けど、本当に綺麗な髪だな。
…ああ、それを言うなら持ち主もか…。
ゼロスは、美形――…っていうより、美人って感じがするな)
自信満々に口にするだけあり、テセアラとやらの神子と名乗った青年の容姿は見目麗しい。艶やかな緋の長髪は、オールドラントの英雄としての痛みを知る聖なる焔を彷彿とさせ、落ち着かない気分にさせる。但し、纏う雰囲気は全くと言って良い程に違う。例えるなら、彼は冬椿。希望(いのち)凍える闇白に畏怖の鬼火の如く灯る唯一の朱陽。儚き瞬間(いのち)を終え、根元から落ちて白銀に面をあげる姿は、
まるで――…、 断罪の跡
「…あー、そのー、そろそろジロジロ見るのはやめてもらっていいかなー?
俺様、減るから。すり減っちゃうから」
流石に居た堪れなくなったゼロスが溜息と共におどけると、我に返ったらしいガイが慌てて両手を肩の上にして、謝罪の言葉を口にした。
「あ、悪い」
「ま、いーんだけどさ。どーしかした? みょーに小難しい顔してさ」
それはもう一心不乱の様子であった金髪の好青年に、ゼロスは興味本位に訊く。助言や力添えを行うつもりなど毛頭無し。待人の合間の暇潰しとして、持ち掛けただけの話題。
「あー…、まぁ、その。……色々あってなぁ…」
「なになに、お兄さん背中に哀愁が漂ってるねー。ひゅーひゅー。
俺様で良ければ、慰めてあげよーか?」
冗談とも本気ともつかない口調で魅惑的なアーモンドの瞳を猫のように閃かせる神子に、ガイは弱りきった様子でお手上げポーズを取って見せる。
「仮にも神子様が口にする事じゃないと思いますよ」
「いーんだよ。俺は神子っても、…――、」
「……ゼロス?」
不意に――…、神子と身分を名乗る青年の軽口が止まり、横穴洞窟の入り口を凝視するのにガイは晴れ渡る青空のような透明な眼差しに警戒の色を纏わせ、肩を緊張させた。危険な気配は感じない。けれど――朱牡丹のような華やかな存在感を主張する神子は、確かに――…、
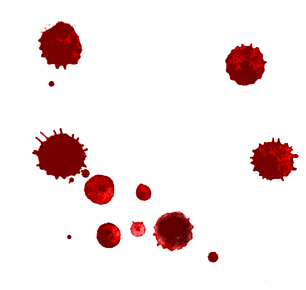 脅えて いた
脅えて いた

テイルズファンなら大概分かると思うんですけど
魅惑のアホ神子を登場させました
裏切りの神子のシナリオが物凄くツボで・・・!
クラパパかアホ神子かの選択で
ナムコのドSっぷりに翻弄されたのはいい思い出です


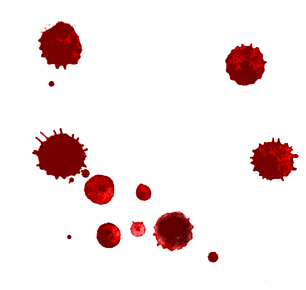 脅えて いた
脅えて いた 