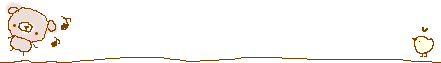
がーるず・ぶらぼー
〜ばにらあいす〜

「………」
風呂上りの濡れた金髪を丁寧にタオルで拭いながら、ランバルディア王家の皇女であるナタリアは、公務の際の毅然とした自身を何処かへ置き忘れたかのように、放心した様子で椅子に掛けていた。
「…ナタリア〜? どったの?」
そこへ丁度風呂からあがり部屋着用にしている服装へ着替えた少女が声を掛ける。普段は頭の両脇でぴこぴこと軽快に跳ねるツインテールは、今は濡れて、愛らしいカールを描きながら、桜色の頬へ張り付いていた。
「えっ? …ええ、…」
呼びかけに応じてハッと我に返る様子を見せるも、直ぐに物思いに耽る姫君に、アニスは両肩を竦めて携帯冷蔵庫からバニラアイスを取り出す。譜業馬鹿とハサミは使いようだ。こういう機能が欲しい、こうしたら画期的だ、と適当に希望を口にするだけで次回には叶っていたりする。
「考え事もいいけどさー、とりあえず髪拭いちゃいなよ。風邪ひくよー?」
「…ええ ……」
生返事を返すばかりの弓使いの姫様に、アニスは、はぁーと長めの溜息を吐く。
「あ、のさ。そんなにアッシュが心配?」
「えッ!? い、いえっ…、 そんなことないですわッ!!
そういう事じゃないんですのよ、別に。ただちょっと…考え事をしてただけです…」
その考え事というのが、婚約者のアッシュ――正確にはオリジナル・ルークのなのだろうと、見え透いた嘘で場を取り繕うとするお姫様に、世間の荒波にもまれて、やや間違った方向へ鍛え上げられた少女は、再び溜息を吐く。
「そんなに気になるなら、ナタリアも行けばよかったじゃん?
そりゃ治癒師がティア一人だけになるのはキツイけど、まぁ、大佐はベラボー強いし、フリングス将軍も少しは治癒術使えるらしいしさ。ルークもあれで結構頼りになるし。なんとかならないこともないっしょ」
「……そういうわけにもいきませんわ。
私は、ランバルディア王国の代表としてこの戦いへ参加していましてよ。
大義に私情を挿むなど、為政者として言語道断ですわ」
「はー、お堅いというか、ご立派というか。さっすが、ナタリアだよね」
アイスを一口、銀色のスプーンで掬って口にする。冷たい甘さにきゅー、と感激の声をあげて、アニスはベッドへ寝そべった。お行儀が悪いですわよ、と窘めるそれは当然聞こえない振りを決め込む事にする。
生乾きの明るい金髪を面積の広い白のバスタオルで拭い切ると、王女として醜態を晒す事が無いように、くるくると毛先をコテで巻いてゆく。後は就寝するだけなのに、何とも用意周到だ。何時なんどき敵襲を受けてもおかしくない立場にある為、全くの徒労とも言い切れないのだが。
万民に愛され、等しく万人を愛する、ナタリア・ルツ・K・ランバルディア王女。
自身の胸の内に募る淡い恋心よりも、国を護り民を導く為政者としての矜持に重きを置く少女は、本当に理解しているのだろうか。幼馴染として共に育ってきた青年が、何を目的にして、元・婚約者の下へと向かったのかを。
(…や、ナッちゃんの性格だと、やっぱわかってないよね。絶対。天然も考えもんだわ、こりゃ)
口の中で蕩けるアイスが美味しい。
スプーンで掬い取りきれないカップの内側のバニラをペロペロ舐めながら、アニスはゴロリと仰向けになった。
「ねー、あのさー、ナタリア」
「? なんですの?」
就寝前の身支度を終えたらしい金髪の王女は、相変わらず奔放な格好でいる少女に目線を遣って、小首を傾げた。
「アッシュとの事、どうするつもりなワケ?」
「…どうする、って…何の事ですの?」
問われる言葉の意味を捕らえきれずに、綺麗な瞳が困惑に揺れているのを見て取り、アニスは盛大に溜息を吐いた。
「だーかーら、結婚とかそういうの考えちゃってるわけ?」
「………!」
天然お姫様には直球で行くしかないと方針を改めた導師守護役の少女は、ズバッと疑問を口にした。
「…け、っ、…え、えええ。
そ、そうですわね。婚姻ということですわね。
……ええと、 」
赤くなって口籠る様子を見る限り、悪くは思っていないのは明白だが、そこまで考えていなかったというような態度に、やっぱり、とアニスは内心で呆れる。
「…親同士が決めた婚約者だったんだろーけど、今の状況じゃ、そんなの無効じゃん?
アッシュは王家に戻るつもりは無いみたいだし、でも、ルークとなんてもう考えられないでしょ?」
「…… そう、 ですわね。
ルークを否定するわけではありませんが、私が将来を誓いあったのはアッシュですわ。
それに、ルークにはティアがいますし」
「あー…、そだね」
惜しいというか、全然違うというか、残念と言うか。
ティアがルークの事を、恋の対象として捉えているのか、それとも手の掛かる弟程度の認識なのかは不明だが、少なくともルークは違う。あの見ている方が恥ずかしくなる位に健気で純粋な赤いひよこは、無駄な色気を振り撒く年上美人しか目に入っていない。あんな態度では当人にもバレバレだろう。大佐は大佐で、ルークには妙に甘いというか、アレは絶対に猫可愛がりしている。
「…こういう事さ、他人が口出すのをどーかと思うんだけど。
アッシュと国、両方とも手に入れるのは無理だよ。どっちか片方だけ。
どっちを選ぶとか決めてあるの?」
「……随分と不躾な質問ですわね」
「自分でも、そー思う。お節介だよね。他人のイロコイなんて、基本的にどーでもいいんだけどさ」
――大切な幼馴染二人に同時に裏切られて、それでも毅然と微笑んでいられるだけの強さを――、確かに『王女ナタリア』は有しているが、困難を共にする旅の仲間である少女にはおそらく、持ち得はしないだろう。決意と信念に輝く碧い瞳を涙に滲ませて泣き崩れるのは彼女だ。
「…わたくしは…、 」
言葉を――、呑み込み俯く。風呂上りの白い項に金の後れ毛がハラリと流れて落ちる。
「大事、ですわ …、 アッシュの事も国の民も愛しています。
どちらかしか選べないというのなら ――、 」
「――ゴメン。やっぱいいよ、言わなくて」
「…アニス?」
自分から言い出したくせに、前言撤回とばかりに答えを遮る人形士の少女に、ナタリアは安堵しながらも、不思議そうにした。
「あー…、別に興味とか好奇心とかそういうのじゃないから。
ナタリアが何もかも捨てられる位にアイツに本気なら…、その――…」
「…わたくしが、どんなにアッシュへ想いをぶつけたとしても、困らせるだけですわ。
アッシュはわたくしを見てくださりませんもの」
「え」
――思わぬ不意打ちだった。しかも、結構なクロスカウンター。驚きに飛び起きる人形士に、ナタリアは柔らかな苦笑を浮かべて続ける。
「…アニスも気づいていますわよね」
「いや…、えと、その――…」
流石というべきか、王女の肩書は伊達じゃない。美しい思い出の中で将来を誓いあった婚約者が、既に別の未来を見据えていると知り、それでも微笑んでいられる。虚勢なのか本気なのかは、十三歳の少女には判断不可能だが、ナタリアは現実を静かに受け入れている様だった。
「別にいいんですのよ。二人ともわたくしにとって大切な幼馴染ですもの。それに、二人がそういう関係になったとしても、…なんというのかしら、嫉妬? ですの? そういう気持ちはわきませんもの。どちらかというと、二人が幸せになるという事の方が嬉しいですわ」
「…うっわ、寛容〜…」
「そうでもありませんわよ」
あまりの物わかりの良さに唖然とする少女に、ナタリアは含みのある微笑みを浮かべる。
「例えば、アッシュの隣に何処の馬の骨とも知れない女性がいましたら、絶対に許していませんわ」
「…ふぁ〜…、そんなもん?」
得体の知れない女はNGで幼馴染の男ならOKという判断基準が理解不能だ。確かに、身近な相手という分マシなのかもしれないが、まだまだ異性文化の根強い今日(こんにち)にあって豪気な事だ。そういえば、賢王と名高いマルクトの現皇帝も結構な思考の持ち主だったと思い出す。
「なーんか、凄いよね。私だったら、そんな素直に応援出来ないと思う」
ごろり、アルビオールの鋼鉄の質感を視界にしながら、アニスは参ったとばかりに零した。
「…幸せになって欲しいんですの。
わたくしは、お父様や臣民に愛されて、十分に充たされていますのよ。
これ以上を望むのは傲慢というものですわ。
だから、二人が幸せになればそれでいいんですの」
「んー…、やっぱわかんないなぁ。
ガイとアッシュがキスしたりSEXしたりしてもオールオッケーって事でしょ?
まぁ、あの二人なら視覚的にはOKだけど、ちょっと想像つかないなぁー」
ゴドッ。
突然の鈍い物音に何気なくナタリアの方を振り向くと、薄い桃色が上品な化粧水の瓶が床にゴロゴロと転がってゆくところだった。
「ナタリア?」
「……アニスッ…」
「んあ?」
すっとぼけた返事をしてくるあけすけな少女に、ナタリアはこれ以上無いくらいに赤く染まり上がった顔で、キャンキャンと非難を浴びせる。
「ななな、なんて事をおっしゃいますのッ! はしたないですわっ!!!」
「…って、ラブ&セックスは当然じゃん?
寧ろ、そういう方向にいかない方が異常だよ。熟年カップルならともかくさ。
二人とも全然若いし、体力も精力も有り余ってるっしょ」
「いやっ!! それ以上、おっしゃらないでっ!!
駄目ですわッ、そんなそんな、――…そんな…ッ」
可愛らしい容姿の少女の口から次々に飛び出す、あまりにも直接的な言葉に対し、免疫を持ち合わせないナタリアはいやいやと耳を塞いでしまう、純情天然なランバルディアの箱入りのじゃじゃ馬姫の反応に、アニスは目を丸くした後――満面の笑みを浮かべた。普段はツインテールが揺れる頭にふたつのツノが生えて見えたのは、おそらくただの錯覚ではないだろう。
「男女のカップルじゃないんだから、どっちも抱けるし、抱かれる側になれるもんね。
ナタリアはどっちがどうだと思うー? 年齢でいえば、ガイがリードするんだろうけど、例の女性恐怖症があるもんね。ソッチの経験ってゼロでもおかしくないし、でもアッシュも見た目はいいけどあの性格じゃー、女は寄り付かないと思うのよね。性欲処理とかで店に行ったりもしなさそうだしさ」
「……せっ、せいよっ…! あ、アニスッ! ふしだらですわよっ!!」
「ふしだらって、年頃になれば当然じゃん? こんな猥談。
神託の盾でも日常茶飯事だよ。ま、あたしは導師守護役を仰せつかってるから、流石に参加はしなかったけどね。男同士の恋愛も別に珍しくも無かったし。ナタリアは? 全然、こういうの興味無いの? アッシュがどんな顔でSEXすんのかとか、興味津々だけどなー、あたしは」
「あ、ああああ、アニスッ! はしたないですわよっ!!」
「それさっき聞いたー。で? 興味ある? 全然興味無い? どっち?」
「……そ、それは」
空いている方のベッドに火照りが収まらないまま、ナタリアはゆっくりと腰を下ろした。
「わ、わたくしだって、全く無いわけじゃ、それは…、た、多少は……、その…」
恥じらいながらもそれなりに興味はあるらしいランバルディア王家の姫君に、アニスは確信犯的な笑みを浮かべた。
「さっすが、ナタリア。話がわかるぅー☆」
「二人で何の話?」
きゃいきゃい騒ぎ立てる少女たちの中でも、おそらく最も真面目でお堅い性格の第七音素術師が、髪を整えながら浴室からひょいと顔を覗かせた。
「あー、なんでもないなんでもない」
流石にティア相手にガイとアッシュがデキたら、どっちがヤられる側だと思う? なんて下ネタは無理だ。なんというか、本気で殴られそうな気がする。あの堅物奏長の妹だけに、慎重にならざるを得ないところだ。
「そう?」
偉大なる始祖ユリアの子孫である優しいブラウンの髪の少女も結構な箱入りだ。無論、兵士としての訓練を受け、実地もこなしているので、単なるお飾り人形とは一味違うが。頬の赤味が取れないままのナタリアは尚もティアに問い詰められているが、助け舟を出せば藪蛇だ。素知らぬ顔をしながらベッドに潜り込む。この先もし二人がデキたらイチャついてるシーンの写真でも撮って何処ぞの恥じらい王族に売りつけられないものかと、とことん商魂逞しい人形士の少女なのだった。
 ・・・あの二人ならリバでもいけるよね☆
・・・あの二人ならリバでもいけるよね☆

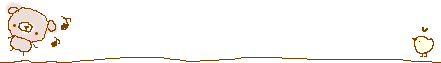
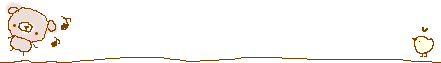

 ・・・あの二人ならリバでもいけるよね☆
・・・あの二人ならリバでもいけるよね☆