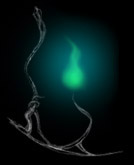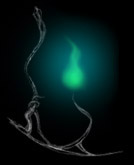傍へ――、鼓動を感じさせて、
傀
儡
第一話
あなたは 、まるでニンギョウのよう
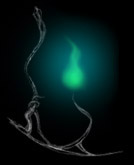
リヴァイアス。
果て無き宇宙を彷徨う子ども達の乗る戦艦(の名を、そう呼んだ。
――――――――――――――――――――
『M-03』と銘打たれた病魔。
恐るべき感染症は、その発症者もろとも隔離区画へ封じ込められた。
得体の知れない伝染病が蔓延したのが、つい、二週間前のことだ。閉塞された空間における、なんら対処の方法の無い恐怖。
これが、一般社会との交流が絶たれていなかったのなら、おそらくは、ずっとよい方法も模索出来たであろう。
いや、例えば、正体も直ぐに判明し、このような大事にはなっていないかもしれない。が、無念な事に、今現在リヴァイアスに搭乗するのは、宙行事故によって一時の避難口を求めた少年少女達だけなのだ。
そう、圧倒的に人員も物資も知識も、足りなさすぎる。
八方塞がりの状況で選択されたとも言えぬ、余地のない選択。
選ばれたのでも選んだのでもなく、その方法しか無いのだから。
理路整然とした理屈だ。何事も、何者も、異論を挟む事の出来ぬ現実に、そう、VGのエースパイロットである少年も切り捨てるような気持ちであった。
――――――――――――――――――――
散々、執着したら
――――――――――――――――――――
「隔離計画に異存のある者はいないか」
一応の確認を、尾瀬がしているのを、その隣で相葉祐希は感慨無く聞き流していた。
仕方がねぇ。
としか、言いようのない現実が実際目の前にあって。
例えば、気丈な副艦長が声高に反対の異論を挟んでいるのも、他のクルー達のような不快感は感じなかった。
諦めれば楽なのだ。命にも執着せず、ただ、行ける場所まで進み続けるだけ。その果てに朽ちようとも、それはやはり仕方がないのだろう。
いけ好かない神経質なクルーに理想を語る少女が言い負かされるのにも、何の感情の波立ちもない。
状況を甘受するわけではないが、それでも藻掻いても足掻いても、どうしようもないということ位理解出来る年だ。
理解も同意もいらない、と。
吐き捨てた同期の言葉が、何故かずうっと頭の奥で響いていた……。
――――――――――――――――――――
同僚――VGを繰る金髪の少女の住処である簡易テントで仰向けに寝転がり、相葉祐希は、もともと無愛想な顔に不機嫌さを滲ませている。
「なーに、不景気なツラしちゃってるわけ?」
揶揄混じりの少女の声に、祐希は更にふてくされるが、彼女はそう気にした様子でもなく会話を続けた。
「隔離計画、だってさ。なーんかホント、継ぎ接ぎだらけよね。
ありあわせのパーツかき集めて、やっと前へ進むって感じしない? あーあ、失敗だったかなぁ、リーヴェ・デルタに残っちゃったの」
「…今更、そんなこと言ってもしょーがねェだろ」
「ま・ね。結構な体験させてもらってるし、これはこれで寧ろ面白くはあるんだけど」
不満を滲ませてカレンはぼやく。
「………もうそろそろ、終わりにしたいかなぁって感じかな。飽きちゃった」
その、余りにケロリとした言い草に、エースパイロットを勤める目つきの悪い少年はジロリと相手を見遣る。
「おい、お前」
「ん、何?」
無防備に見返してくるカレンへ、癖の強い黒髪をした少年は両の掌から零れるように、言葉を投げかけた。
「…執着しねぇのかよ」
「何に?」
不必要な程なカンの良さを誇る少女とて、余りに唐突な質問で意味を捉えきれずに訊ね返す。
「………」
会話がテンポよく進まなかった事が気にくわなかったのか、祐希は無言で向こうをむいてしまう。そんな同僚の子どもっぽさに嘆息して、少女は音楽チップの整理を続けた。こうなったら、以降のやり取りは時間と労力の無駄にしかならないと、よおく理解している。
意固地になったお子さまの相手なんて、やっていられないというのが正直な所。
「隔離計画かぁ…実際、まいっちゃうわよね。ま、仕方がないってヤツだけど?」
チップをジャンル別に分けながら、カレンはひとりごちた。
特に、話し相手へ聞かせようと思ったわけでもなく、ただの独り言の範疇のそれ。少年も事を把握しているのか、黙って聞き流す。
「隔離だなんて聞こえはいいけど、要するに見捨てるのよね。
ホント、思い切ったことしちゃって。在る意味、彼が一番負担を感じてるんじゃないかしらね」
「……誰のことだ」
「尾瀬くんよ、尾瀬イクミ君。
彼、元々そういうタイプの人間じゃないっぽいでしょ。無理してるのが、ありありじゃない? いっぱいいっぱいよねぇ、たーいへん」
まるっきり他人事と言わんばかりの金の髪の少女へ、祐希はチッと舌打つ。
「……知るかよ」
「………」
口先だけでは尾瀬を見捨てるような素振りでいるのだが、酷く気に掛かっている様子なのは一目瞭然。
素直じゃないなぁ、と。
かるーく肩を竦めて、小振りな顔立ちをした少女は目に留まった一枚の音楽チップをプレーヤーに填め込んで、軽快な音を楽しむ。
と。
「祐希ぃ〜、ゆうきぃっっ!!」
?
微かに、聞き覚えのあるようなそれ。
己の名を呼ばれる隣人は、声の方向を辿りながらも何かしらの行動を起こす素振りは見られない。
カレンはプレーヤーの一旦停止を行って、ちらりと天才たる少年を見遣り、ついつい、口をついた。
「………呼ばれてない?」
「…あぁ。」
どうやら、無視を決めこんでいたようで。
煩わしそうに応じる祐希に、少女は、ま、いいけど? と、その意思を尊重する。
要するに面倒事を避けたいだけ、でもあるのだが。
基本的に、他人への干渉や他人による干渉。その出来事によるゴタゴタの波及は、聡明でいてずぼらという面妖な性格の少女の望む所ではない。
「祐希ってばぁ〜、祐希!! ゆうき、ゆうきゆうき!!!
相葉ゆーき!!! 返事しなさーーーーーいっ!!!」
喧々囂々、捲し立てる少女のそれ。
ちらり、と。
名指しでご指名される少年を伺えば、苦い表情をしてながーい溜息をついている。
「観念したら?」
ぼそりと呟けば、例の目つきの悪いそれでギロリと睨まれた。
黙っていろということらしい。
まるで、ブルー並の傍若無人だが、少々拗ねたような表情の変化が見られる辺り可愛気は充分か。
「チッ、ったく。るっせー」
仕方がない、といった風情で、ひねくれ坊主ならぬ。優秀なパイロットは幼馴染みの元へと行ってしまう。
「ホントに素直じゃないわよねー、心配なくせに?」
と、言う。
同僚の感想を耳にすることもなく。
――――――――――――――――――――
壊して、投げ捨てた
――――――――――――――――――――
何処にいるのよー、と。
リヴァイアス名物、相葉兄弟の幼馴染み『蓬仙あおい』は大きな声を張り上げていた。艦内は悪夢の感染症が蔓延り、クルーの人数を激減させ。残った生徒達も『M−03』を懼れる余り奇妙な静けさが支配している。
そんななか、これほどの声で叫べば否応なく他の人間の耳にも届くだろう。故に、危険性もある。
どうせ未来は無いものと、明日の命も知れぬものと、暴走する少年達の毒牙にかかるかもしれぬのだ。実際、そのような事件は何件も起こっている。それらは全て、未然に防がれてはいるのだが、いつか事は起こってしまうだろう。
あおいとて、現在の艦(ふね)の様子を察せぬ程、愚鈍ではない。
十分に危険性を理解し、承知しつつ、このような行為を行っているのには彼女なりの理由というものが存在するのだ。
そう、どうしても。
なにがなんでも引けぬ理由が。
(……昂冶……、)
胸の前で、きつく握った両手を組み合わせる。俯いて、一つ、小さな溜息をついた。
「おい」
「っ、祐希!?」
そんな少女に、背後から不機嫌そうな声が投げかけられる。
聞き間違うはずもない、幼馴染みのそれに、あおいは勢いよく顔を上げた。
「…何の用だよ。
人の名前、あんな大声で連呼しやがって。迷惑だ」
「ゴメンっ、謝る。
ねぇ、それよりっ。祐希ッ! 昂冶の事なんだけど、様子を知りたいの!」
「………兄貴の?」
片眉を上げて、思いきり不審そうにしている年下の少年へ、あおいは一瞬戸惑い、落胆をみせた。
「――…知らないんだ、昂冶のこと……」
思わず、事を知らぬ人間を相手に罵詈雑言を浴びせそうになるのを、なんとか理性で抑え込む。
「そう…なんだ。ふーん、トコトン興味ないんだね、もう、お兄さんなんてどーでもいいんだ?
祐希は。そういうものなんだね、あたし、兄弟いないし。
普通、そうなのかな。どうだろ。……わかんないけど。
ちょっと………あれだよね……」
「? ンだよ、兄貴がどーだろうと、俺に関係ねーだろ…。
一々、あのバカ兄貴のことで俺に話を持ってくンなよな」
あおいといえば、何時もハキハキしており、含みのある物言いをするタイプの人間ではない。らしくない、何処か棘のある言葉に、謂われのない非難だと祐希もムッとする。
普段なら、これ以上は何を言っても無駄だと、少女の方が早々に身を引くのだが。今回ばかりは彼女とて譲れぬと、尚も言葉を重ねた。
「……冷たいね、祐希。
ホントに知らないんだ、昂冶がキャリアとして隔離区画に連れて行かれたこと。尾瀬と一緒に、ブリッジに……いるくせして。
あんな中枢にいるくせして……、隔離計画を決めた人たちの中にいたくせしてっ……知らないんだッ!?」
歯止めの効かぬ感情が、後から後から、堰を切ったように流れ出る。
悔しくて、情けなくて、キッと睨んだ先の少年の、驚いたような途方に暮れたような顔が滲んでいた。
「おいっ…、なんで泣くンだよ……ッ」
「ウルサイッ!! 信じられない、ホントに知らなかったんだ!?
お兄さんだよ!! 昂冶だよ!? もう、三日も前だよ、連れてかれたの!!
感染の危険性があるからって、全然連絡も取らせてもらえなくて、様子も教えてもらえなくて!! でも、あたしっ。祐希がブリッジにいるし大丈夫かなって思ってた!!」
悔しい。
「祐希が、昂冶のこと気が付くの当然だと思ってた!!」
そんな、自分が。
情けない。
「なのに、知りもしなかったんだ!? 昂冶のことなのにっ、赤の他人じゃ無いんだよ!?」
そんな、バカな弟が。
赦せない。
「尾瀬がテロ野郎のバカなら、祐希は大バカチキン野郎よ!!」
そして、……。
「あたしっ何にも、出来ないのに! 出来な、かった……よぉ……。
あたし…、あたしッ……一緒に、いたっ・のに……つれてかれ……て、……」
なにより、も。
「手、……っ。
のばせなかった、の……」
――――――――――――――――――――
粉々になった、人形は
――――――――――――――――――――
ガーディアンズと銘打った、それはただ呼び名を変えただけの一方的な暴力組織。正義を法を、掲げる姿は独善的で、心を伴わぬ服従は、ただ苦痛だけを与えるのみ。
彼らが例え絶対的に正しくあったとしても、理性と感情とが相反する存在である以上、事実憎しみはその場に降り積もる。
そう、少女の胸の内に――…。
キャリア隔離の宣告は突然に、防毒マスクで顔面を覆ったガーディアンズメンバーが数人でやってきて、押しつけた。有無を言わせぬそれ、必要なもの半時以内に纏めろと居丈高に言いつけられ。
驚きを隠せぬ表情のまま、それでも瞳に絶望の色を滲ませ大人しく指示に従う幼馴染みに、当然の様に意思の強い少女は苛立った。
『なんでよ! 黙って従うことなんてないわよっ、昂冶!!
なんにも証拠なんてないのよ、なんでキャリアだってわかるの!? 変じゃない!!』
そう、捲し立てるのも虚しく、少年は此方を振り向きもせずに荷物を纏めて行く。まるで負け犬のような姿に益々彼女は怒りを持った。
盲従を強要してくるガーディアンズにも勿論、その憤りはあったのだが。何より、幼馴染みの不甲斐なさが腹立たしかったのだ。
『ちょっと、昂冶!! 訊いてるの!?』
『触るなッ!!』
言葉と同時に出た手を、思わぬ語気の荒さが止めさせた。
『……なっ、なによっ…』
『これが、どんな病気か知ってるだろ。
……死ぬんだぜ。触るなよ、あおい……』
『――…ッ』
突きつけられた拒絶。
途中まで伸ばされた指先が、奇妙に中空で留まったままで。
今ある世界が、そう、例えば穏やかな地球の空の下であったのなら。
それがどうしたのかと、はね除けられた、――…のに。
死が日常的に隣り合う世界で、実感を伴って在る空間で、まるで他人事のように『大したことではない』と、口に出来るほど……人は、強くはない。
――愚かではない。
届かない指先、いや、恐怖に動かぬそれ。
昂冶という名の少年が、まるで幼馴染みの心を見透かすように、その事実を暗い瞳で掠め見て、ただ、一言。
サヨウナラ、
とだけ。
残して、去ったのだ。
――――――――――――――――――――
「あたし、……あたしっ、昂冶を見捨てたんだ!!
感染るのが嫌だったのよ、死にたくないからっ……あの時、昂冶に手を伸ばせなかったんだ!! なんで、っ、…………なんでよぉぉぉっっ!!!!」
優しい世界にいたのなら、気付かずに済んだのに。
大切な人を見捨ててまで、自分が生きたい――生き残りたい。
そんなにも、……こんなにも、醜かったなんて!
「……あおい…」
まるで壊れたかのように泣き叫ぶ少女を前にして、祐希はただ硬直するだけだ。今までは常に『お姉さん』の存在であった彼女。
何時も自分をガキ扱いして、一人前の男として見ることもなかった年上の少女が、この腕に、胸に縋って泣きじゃくる。
混乱するだけの黒髪の少年の頭を、コンッ、と、何者かが後ろから小突く。
「………っ?」
あおいを宥める為に姿勢はそのままで、首だけで振り返って背後を確かめると、同僚のパイロットだ。
なんだよ…?
と、視線だけで問いかければ、辺りを窺うようにとの目配せ。
訝しがりながらも合図に従えば、周囲からよからぬ気配を感じて黒豹にも似た雰囲気を纏う少年は内心で舌打った。
少女の泣き声が、お世辞にも品がよいとは言えぬ連中を刺激したようだ。
(早く、ココ移動した方がいいわよ?
アッチ事を大きくするつもりはないと思うし、とりあえず、アタシのテントに非難した方がよくない?)
(……ああ、そうだな)
祐希にしたところで、いちいち血の気の多いバカの相手をしていられない、というのが本音だ。この非常事態で余計な体力は消耗したくない。
「おい、あおい。
……とりあえず、移動するぜ。いいな」
「………?」
明らかに不服そうに、泣き腫らした目で見上げてくる少女に対し、祐希は嘆息した。
「ンなとこでいつまでも喚き散らしても始まンねーだろ。
……ちゃんと話聞くから、頼むからよ。こっち、来てくれ」
「………」
最近は反抗期も重なってか、全く可愛気のない口しかきかなかった相手が、急に下からの物言いをしてきたものだから、あおいはとりあえず素直に頷いた。
色々と、納得していないことはあるものの、確かにこうしていても何事も解決しないことは理解しているのだろう。
結局、その場を立ち去った三人を追いかける影はなく。カレンの気の利いたフォローのお陰で、事なきを得たのだった。
――――――――――――――――――――
もう元には戻らない
――――――――――――――――――――
幼馴染みの悲痛な訴えは、金の髪をした同僚のテントに移動してからも延々と続けられた。しかし、それは先程のような感情的なものではなく、ただ、切実にキャリアとして連れて行かれた少年の無事を願うもので。
くれぐれも、昂冶の事をよろしくね、と。
何度も何度も念を押しつつ、あおいは元の部屋へと戻っていった。
艦内の危険な状況を案じた祐希の、VIPルームへの移動の提案や部屋までのガードを全て、『特別扱いは嫌だから』といつもの年上然とした顔で断って。
「そんなに気になるんだったら、無理にでも移動させちゃえばよかったのに」
同僚のそんな言葉に苛立ちを感じ、祐希はウッセェな、と悪態をついた。
普段にも増して不機嫌な少年の様子に、触らぬ神に祟り無しを決め込んだのだろう。カレンは、耳元に流れるサウンドに集中してしまう。
片や、パイロットの少年は幼馴染みに頼まれた件に関して、頭を悩ませていた。
(……隔離、区画か。
確か俺のIDは登録されてねーんだよな。ヘイガーのヤツは、尾瀬の犬に成り下がっちまてるから当てになんねーし……)
正攻法でいったところで、隔離者の状況把握や、ましてや面会など。
(…無理に決まってる、か)
なら。
「おい、カレン」
「! ……何よ、なにか用?」
長くもないつき合いの中で、この天の邪鬼坊主が自分の名前をまともに呼ぶ時は何事かの頼み事がある事を察しているカレンは、耳元からイヤホンを外して少年に向き直る。
「…お前、携帯端末持ってただろ。貸せ」
「…………………………あ、なーるほど。
――仕掛けるなら、システム更新する夜中1時がうってつけよ?」
軽くアドバイスしながら、はい、と端末を手渡してくる。
「……悪りぃな」
「別に、いいわよ。頑張ってね♪」
にこやかな応援を背に、祐希は少女から借りた小型の端末を手に、行く――。
そう、
――…捕らわれた、兄のもとへ。
――――――――――――――――――――