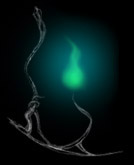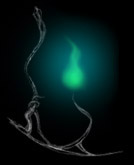傍へ――、鼓動を感じさせて、
傀
儡
第二話
あなたは 、まるでニンギョウのよう
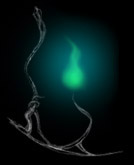
――――――――――――――――――――
最低限に絞られた照明、飢餓を凌げる程にしか与えられない食事。粗末な寝床には、既に事切れた人間の体が、無造作にほうっておかれている。
感染症の末に果てた死体は日数が経過しても綺麗なままで、逆に、今在る悪夢を際だたせた。現実感のない狂気が、人の心を肉体よりも早く死に至らしめる。
部屋の隅で膝を抱えたまま、ずうっと眠らない生徒。
虚空に視線を送り、一人、何事かを呟き続ける生徒。
自虐を繰り返し、血文字を床に書き殴る生徒。
誰もか彼もが、真っ当な精神を破壊され、まともな受け答えが出来るものはほんの一握りだけだ。
その、稀少な人間たちによってやっと、隔離ブロックの配給が回っているというのが現状。
好きこのんで感染者達の巣に足を踏み入れる者などいるはずもなく、彼らは死に直面するにも関わらず、その命尽きる時まで自分たちの食事配給などを自らで行わなければならない。
その、一握の存在の中に、彼――…相葉昂冶は、いた。
夜中となれば、精神異常をきたしていない生徒達も皆、昼間忙しく立ち働いた疲れを癒している。粗末な毛布にくるまり、思い思いの場所で休眠を取る。
そんな中、曇り無い空色の眼差しを陰らせ、昂冶は一人寝付けずにいた。
先の事に考えを巡らせれば、思考は闇に呑み込まれ光などただの一片すら見いだせずに。
(配給も少しずつ減っていってる……やっぱり、外の連中は俺達を見殺しにする気か……)
それも、仕方のないことだと、少年は氷ついた心で結論づけた。
他者を思いやる気持ちは大切だ。
けれど、それは我が身の危険を感じない安全な場所でぬくぬくと生きていられればの話。
明日をも知れぬ閉ざされた世界で、人を愛することも、人の温もりも、人の心も。
失って、いく。
「………」
ぎゅ、と己の心の臓あたりを掴み、少年は俯いた。
(ねむれない…少し、歩いてくるか……)
隔離区画に指定されている範囲は意外に広い。
一時の安らぎを得る生徒達を起こさぬように、昂冶は足を忍ばせて歩き出した。
――――――――――――――――――――
隔離区画の中央から離れると、照明も非常灯だけとなり、人気も無く寂寥感だけが遠くまで続いている。
静寂の中、己の鼓動と靴音だけが何重にも広がりを作る。
「……さむ…」
星の海を漂う戦艦の中では寒暖の格差は少ないが、それでも一人でいる肌寒さに昂冶はそっと腕を組み合わせた。
「………」
始まりは、何だったのだろうか。
少年は歩く事に疲れ、乱雑に置かれたコンテナの影に腰を下ろして考える。
「……リーヴェ……デルタ…」
宙行士養成所リーヴェ・デルタ。
原因不明の事故により、養成所は制御を失いゲドゥルトの海へ墜落しようと、した。
教官達の決死の行為と彼ら尊い犠牲により難を逃れたリーベ・デルタの生徒は、そのままこの巨大な黒の戦艦へと避難したのだ。
「黒の……リヴァイアス…か」
直ぐに、救助が来ると信じていた。
当面の危機を凌いで、救難信号を出して、後は待つだけだと。
なのに――…。
救済どころか、事実無根の罪を着せられ、次々と現れる正体の知れぬ『敵』。
何故襲ってくるのか、何が目的なのか。
どれ一つ、確かな答えなどなく。
純然たる事実として、彼らは 敵 なのだと。
殺さなければ、殺される。
ただ、絶対の掟がそこにあるだけ。
「……けど、……は…どうせ…」
幾ら足掻いてみても、どうにもなりようがない運命というのは確か、存在する。
余命幾ばくもない命をご大層、大事に抱え込んで過ごせる場所じゃない。
自身の不幸を嘆いて呪い、逃避出来るような、そんな生易しい事。
不可能だ。
虚事のように呆気ない命の幕切れは、既に恐怖も通り越してしまい、何も感じない。
絶望も懼れも、諦めすら。
あるがままを甘受するだけの、思考すら放棄した、まるで。
――――――――――――――――――――
隔離ブロックには何重にも電子ロックが掛けられているが、人の見張りは立ってはいなかった。
その警備は、閉鎖区画にいる人間が感染源を体内に保持したまま艦内へ出る事を防ぐのを主な目的とするものであり、外から第三者が内部へ潜入するのを防止する為のものではない。
そもそも、感染者の巣窟に好きこのんで足を運ぶ酔狂がいるわけもなし。
(――…チョロイぜっ)
VGを繰る若き覇者の一人、相葉祐希は同僚の少女から借りた超小型端末を片手に、電子ロックを次々と看破していた。
元々、天才と謳われるだけあって才能高く、また、このような事柄には興味も強い。そのような相乗効果により、少年の手に掛かればこれらは所謂、朝飯前、というヤツだ。
(…これが……ラストッ………!)
ぴ。
小さな小さな電子音が、完全にロックが解けた事を知らせる。
(……よしっ。じゃ……これで………っと…)
一旦、解除されたセキュリティを復活させない為に、自動復旧に制止信号を出して、見た目にはロックが破られていると判らないようにカモフラージュしておくと、少年は身軽な動作で隔離区画に足を踏み入れたのだった。
――――――――――――――――――――
暫く、薄暗い通路が続くと、そのうちに空のコンテナを保管しておく場所に出た。
やはり視界は効かないが、乱雑に置きすてられたコンテナは、結構な大きさの部屋一杯に広がっている。
足下に掲示される順路の矢印が無ければ迷ってしまいそうだ。
裸足でいるせいもあるが、そもそも、この区画が肌寒いのだ。
(……冷えるな。それにしてもこっち側、随分スペースあるじゃねーか………)
隔離区画というからには、もっと狭くて暗い場所にすし詰めにされているようなイメージがあったのだが、余剰な程のペースがあるようだ。
無論、生活に適した場所とは到底言い難いのだが。
(………てっと、兄貴何処いるんだか……。
早く見つけねーと……他の奴ら、寝ててくれればいいんだけどな。騒ぎになるのは流石にマズイ……、―――っ!?)
ひたり、っと、祐希は足を止めて、直ぐ傍のコンテナを背にした。
誰か、――いる。
此方に気が付いた様子が無いのはなによりだが、こんな時間帯にも関わらず起きているヤツが他にも結構いるとすれば厄介だ。
(……収容施設はこの先か…、コンテナの影に隠れて行けば大丈夫だろ…)
幸い、相手はその場を動こうともせずにぼんやりと座っている。もしかしたら、眠っているのかも知れない。いや、それとも――、
既に、物言わぬ躯と形果てたか。
何にしろ、兄でないなら用はない。祐希は相手の様子を窺いながら収容施設を目指す、が。
「………ッ!!?」
思わず、我が目を疑う不法侵入者。
なんたる偶然か、それとも、必然故か。探し求める兄の姿が、そこに在ったから、だ。
――――――――――――――――――――
ふと、気配に気が付いて、昂冶は両の眼を開けた。
それでも視線の先は足下のままで、一体、誰が自分の目の前にいるのかすら理解していないのだろう事は明白だ。
己の前に現れた気配が、無言のままにしゃがみこむが、昂冶は何の反応も返さず、再び瞼を下ろしてしまった。
昼間の超過労働により、肉体は泥に浸かり込んだかのように重く、精神(アタマ)だけは不愉快なほどに興奮してしまっている。
(……やっぱ、眠れないな。
いいけどさ…。別に、………ずっと、こうしてても)
ほんの少し身じろいで、膝を抱きかかえるようにした。
(……さむい…な。
毛布とか……持ってくれば…よかったかな…)
「おいっ、………兄貴……ッ?」
(そういえば、小さい頃とか……。
…よく、こういう風にしてたっけ。祐希と二人で………)
「………兄貴?…」
所謂、大人の事情というものが幼い兄弟の心を傷付けた。
子どもにとって絶対の存在である親に裏切られ、上辺だけいい顔をしてみせる親戚の間をたらい回しにされ。
唯一、頼りとなるのは互いの温もりだけで。
与えられた部屋で、震える心を寄せ合い、一枚の毛布にくるまり抱き合って夜を過ごした事を、覚えている。
今となっては、遠い記憶――…。
「おいっ、兄貴!! なに呆けてンだよッ!!」
「………?」
些か乱暴に昂冶の肩を掴んで揺さぶると、焦点の定まらぬ瞳で小柄な少年は何度か瞬きを繰り返した。
「……ゆう、き…。………、…………!!」
眼の中に映り込んだひとの姿、その彼の名を口にしたことで、一気に昂冶は現状を理解した。
「祐希ッ? なんでここにッ…、ッ、! 放せッ!!」
「………!?」
余りの剣幕に、普段我の強い弟の方が思わずたじろいで手を退けた。
「な、…んだよッ、イキナリ…」
「…………」
祐希の疑問には答えず、感染者である少年は追いつめられた目の色で拒絶だけを返した。
「…おい、兄貴ッ。何とか…」
「触るな!」
「………ッ、?」
他人(ひと)へ遠慮ばかりして気の優しいばかりの、侮蔑の対象である『兄』はそこには存在しなかった。
「お前が何考えてるかなんて俺は知らない。けど、触るな」
感染者としての、相葉昂冶。それは、兄などではなかったのだ。
これが日常での一場面であったのなら、とうの昔に取っ組み合いとなっていたことだろう。だが、日常を非日常へと化する全ての事象が祐希の感情を戒めていた。
「………」
困惑して言葉を失う祐樹。即断即決な性質の少年にしては珍しい場面だろう。
「……何をしに来たかなんて俺には関係ないし、知りたくもない。用が済んだらサッサと帰れよ……死にたくないだろ……」
言い捨てて、昂冶はのろのろと立ち上がる。
「……あにき…」
「………」
以上の問答を背中で拒絶し、病に冒される小さな体を推して兄は歩き出す。
「兄貴ッ」
「…………」
言い様のない不安と切なさが募り、どうしようもなく祐希の心を急かした。堪らず、兄を呼ぶが、振り返るどころか足を止めることすらなく、昂冶は行ってしまう。
「……兄貴…」
長い間、見続けた背中。憧れた兄。追いつきたくて、肩を並べたくて、必死で追いすがって。気が付けば憧憬の対象だった兄などとうに追い越した。
そう、思っていた。
なのに、遙か後方にいたはずの兄の、その背中がまた目の前にある。
――…自分を、見捨てようとしている。
――――――――――――――――――――
『兄ちゃぁんっ…!』
幼い、過去の記憶。
振り返らぬ兄、残像が絡みつく。
『いかないでよぉっ、やだぁっ!!』
泣き縋った昔。
ただ、ひたすらに兄を慕い、無条件に懐いた。
いつも、いつまでも……、
コドモのままでいられたら、いいのに。
兄弟二人を一緒に面倒は見きれないとか、そういう理由だったのだろうと思う。当時、幼すぎて、詳しいことは覚えてはいないが。
兄は親戚の家に、幼い自分は施設に。
今から思えば、似たような境遇の子らが集まる施設の方が遙かに待遇は良かっただろう。兄は、自ら辛い道を選択したのだ。――…年端もいかぬ弟の犠牲になったのだ。
だが、そんな理由など知るはずもなく。また、理解出来るはずもなく。
幼すぎる精一杯の抵抗で泣き叫んでみても、此方を振り向こうともせず、ただ、往こうとするばかりの兄を。
兄に――…。
激しい胸の痛み。
心の内に募る切なさ。
思えば、こんな気持ちだったのだろう。
捨てられたのだと、感じたのだ。
――――――――――――――――――――
「兄貴ッ!!」
過去が、現在(に重なる。
去りゆく兄、もう、二度と逢えないという絶望に支配された記憶が鮮烈に甦る。
あのとき、自分はどうしたのだろう…?
そんな事を頭の端に思い浮かべながら、想い出に囚われる少年は駆けだしていた。
頼りない足取りの兄を捕まえるのは容易い事だった。痩せた二の腕を些か乱暴に掴んで、驚いて此方を降り仰いだ隙をつくように抱き留める。
見栄とか、体裁とか、自尊心とか。
一切の柵から解き放たれた心が、思うがままに、器を揺り動かしていた。
「ゆ、っうき!? なにっ…、放っ…」
「…兄貴に会いにきたんだ……、あおいのヤツに…ここに入れられたってきいた」
拘束される、その痛みに呻く兄の耳元に、祐希は消え入りそうな声で囁いた。
「………あおいに…?
ッ……、祐希…感染るからッ……ダメだ…!」
思い掛けなく懐かしい名を聞いたものだから虚をつかれて全身の力をぬく昂冶だったが、直ぐに現状を把握して抵抗をし出した。
と、いえども、元々腕力で敵うべくもない相手。更には、極度の緊張と疲労に加え、病で衰弱しているとあっては、昂冶に逃れる術もない。
「ダメだって、……放せよ…ッ…祐希…!!」
だが、解放を諦めるでもなくしきりに、放せ、とばかりを連呼し暴れる。
「…………イヤだっ」
「…祐希ッ! なに、わけわかんないことっ……、いいから放せ!!」
恐るべき感染症をその身に宿す兄にとってみれば、この状況下で無茶な弟に与えられるのは拒絶だけだ。それが、精一杯の行為であり、好意。
感染者である己と接触すれば、無論、感染の可能性は高くなる。
それなのに、こともあろうか抱きついてくるなどと。
パニックに陥った昂冶には、抱擁(それ)が何を意味するかなどと汲み取る余裕なんてない。ただ、己の内に在る『毒』が他者を……諍いあっているとはいえ、血の繋がった実弟を殺してしまうかもしれない。それだけしか、考えられなくて。
(……どうすればッ……)
話すら聞こうとしない兄。感染の危険を危惧するあまりに、泣きだしそうな顔をして弟の手から逃れようとする苛立たしい程に優しい兄に。
どうすれば、この胸を突く想いを伝えられるのだろう。
「……祐希ッ…!」
非難がましげに睨み付けられる、その空色の眼差しがしっとりと潤んでいた。ままならぬ状況と背中の痛みが、痩躯の少年の心と体を苛んでいるのだ。
「………にきっ」
それでも、手を緩めることは出来なかった。
今、この腕に込める力を無くせば、そのまま兄との絆を失いそうで。
「………………きだっ…」
――――――――――――――――――――
ぺたん、と。
その場に崩れ落ちた兄を、何処かバツの悪そうな顔でいる弟。
硬質な黒髪と、激しい気性を物語る鋭い眼差しも印象的な少年は、微かに頬を染めて憮然としている。
対する昂冶といえば、白い指先を自分の唇に寄せて呆然としていた。
「……また、明日来るから」
「………え。」
初夏の空のように綺麗な青の眼を瞬かせ見上げてくる、その視線から逃れるように祐希はふいっ、と背中を向けた。
「同じ時間に来るから……待ってろよな…!」
「え。……え?
来るって、……祐希ッ? あ、ちょっ!!」
一方的な約束に反論の暇(すら与えず、身軽な少年は赤のジャケットを翻し外界(の世界へと行ってしまう。
「……感染るから……ダメだって…」
言ってるのに。
「………」
ゆっくりと、まだ感触の残る口唇を冷えた指先で辿る。
途端に自覚して、昂冶はカァッと瞳を潤ませた。
「〜〜なんなんだよ……、一体…っ…」
幼すぎる想いは真っ直ぐにひたすらで、汚れなく。
残酷なまでの純粋さに、否定の言葉を吐き捨てることも叶わず。
ただ、混乱していくのだった。
――――――――――――――――――――
閉鎖区域より、人目につくこともなく抜け出したエースパイロットは、素知らぬふりでセキュリティを元通りにすると足早にその場より去った。
――…頬が熱い。
兄への先程の行為を後悔する気は微塵も無いが、……顔が赤くなるのは仕方がない。
鬱陶しい程にカンの良い同僚にこんな姿を見らたのなら、何を勘ぐられるのか分かったものじゃない、と。
祐希は塒には戻らず、リフト鑑へと足を向けた。
権力者達の城であるリフト鑑には一般生徒の出入りは許可されていない。一人っきりになるのには、うってつけの場所だったのだ。
しかし、――…。
思い掛けない人物に、小型の豹を思わせる少年の動きは止まった。
「………尾瀬。」
先程まで感染者区域にいたという事実が、少なからず祐希を動揺させる。ぎくりと足を止めた天才の呼び声も高い少年へ、今現在の黒の戦艦における覇者は投げ遣りな視線を寄越した。
「祐希か…、もう夜中だぜ。休まないのか」
「あ、…ああ。ちょっとな」
巨大なオブジェのようにリフト鑑の中央スペースに陣取るVGの内部装甲。その前に立ちつくす独裁者の横顔には、感情の一片たりとも浮かんではいない。
尾瀬は、妙に聡い部分がある。いや、寧ろこの察しの良さが本性か。
下手に探りを入れられては厄介だと、祐希は早々に来たばかりの道を引き返そうとするが、呼び止められる。
「……なンだよ、なんか用か」
「…………」
生気の失せた顔色に、二(の眼(だけが異様に鮮やかな輝きで魅せる。
彼が、人懐っこく物怖じせず、誰にでも平等に優しく、時折ちゃっかり世渡り上手で。兄とは違った意味で人受けが良く、快活な性状であったのは既に過去の姿。
今はそう、悪鬼の如き統治者。
彼自身が本質的、かつ、病的に内に抱え込む捻られた絶対正義の下に、無限の星の海原を漂うちっぽけな艦(ふね)で、全ての命を掌握する非情の覇者。
そんな彼だからこそ、傍若無人を地でゆく祐希とて無視するわけにもいかずに、応じたのだが。当の本人が黙り込んでしまった。
「……おい、尾瀬?」
「…………なぁ、祐希」
「なんだよ…?」
やっと口を開いたかと思えば、やはり歯切れが悪い。生来、我慢の効かない性質である少年は直ぐに短気を起こし、幾ばくかささくれ立った台詞を投げて寄越した。
「…用がないなら、俺は行くぜ」
「――昂冶のコト。」
「………っ、………兄貴が、なんだってんだよ…」
いきなり核心に触れられ、殊更、興味も無い様子を演じてみせるが。果たして、感の冴える眼前の覇者に何処まで誤魔化しがきくものか。
「……いや、なんでもない。
悪いな、手間取らせて。もういいから…」
だが、全てを知られているのかという疑念は、完全に杞憂に終わった。中途で言葉に力を失い、尾瀬は再び己の内に沈み込む。
「………?」
平素より更に増して、精神的な脆さを剥き出しにする尾瀬に多少の引っかかりを感じたものの、基本的に『嘘』の苦手な祐希としてはより以上の詮索を逃れるべく、リフト鑑を後にしたのだった。
――――――――――――――――――――
壊れたニンギョウ ハ もうモトニハ 戻らない
――――――――――――――――――――