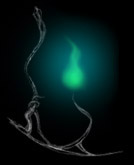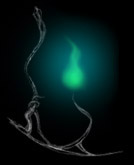傍へ――、鼓動を感じさせて、
傀
儡
第三話
あなたは 、まるでニンギョウのよう
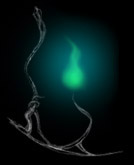
――――――――――――――――――――
兄との逢瀬を果たしてから、次の日夕刻。
通常業務を終えた相葉祐希は、普段通り粗末な食事を終えると、同僚のテントで兄との約束までの時間を潰すために横になっていた。
――…思い出されるのは、触れあうだけのそれ。
有無を言わさず口唇を奪い、声も呼吸も閉じこめた。
(………くそッ…)
何故、あんな行動に出たのか。自分自身の事なのに、訳が分からない。
ただ、驚くべきは嫌悪を抱かなかった事。いや、それどころか、頭と体の芯が痺れて、弾けて、どうにかなりそうな激情に駆られたのだ。
もっと、
触れて。
もっと、
奥の方まで。
あなたに、触れたい。
「………ッ!?」
がばりと、祐希は勢いつけて起きあがった。
栄えあるエースパイロットが、荒削りな端正さを醸す横顔を真っ赤にして固まってしまっている姿は、なかなかに間が抜けていて可愛らしい。
ここに例の同僚でも居合わせたのなら、良い様にからかわれていたことだろう。
(…………じょっ……だんだろ。これじゃまるでッ……!)
まるで?
(くそっ、なんたって……!)
こんな事を思わなければならないのか。
混乱する暴走少年だったが、そこへテントの持ち主が帰ってきた。
「たっだいま、………って。何? どうしかした? 顔、真っ赤よ?」
案の定、一番触れられたくない事を指摘してくるパイロットの少女、カレン。
「うっせぇ!!」
噛み付くように返されて、ふぅん? と、軽く肩を竦めて、それ以上の追求をしてこない分だけ、まだ他の女どもよりは御しやすいのだが。
これが、あの鬱陶しい保護者気取りの幼なじみだったなら、白状するまで延々と、根ほり葉ほり尋ねてくるだろう。
ついには、気分でも悪いのかとか、おなかでも痛いのかとか。
それに比べれば遙かにマシではあるが――…。
「何? ついに自覚しちゃったとか、コ・イ・ゴ・コ・ロ」
「はぁっ!?」
恋、心?
聞き慣れぬ単語に声を荒げる祐希だ。そんな様子に、あら、違った? と、軽く肩を竦めてカレンは何処吹く風、お気に入りの音楽チップを物色し始めてしまう。
「……それにしても、どうだった?」
「なにがだよ…」
憮然として聞き返してくる有能なパイロットに、少女はふぅ、と溜息をつく。
「とーぼけちゃって? お兄さんの事よ。どう、逢えたんでしょ?」
「……ああ、まぁな」
「元気――…とはいかないだろうけど、無事を確認できたんでしょ。何か話した?」
「ああ、少しな…」
「ふぅん?」
会話に精彩さを欠いた同僚の様子に異変を感じ取り、金の髪の少女は小さく鼻を鳴らす。
(……これは、何かあったみたいね…?)
などと、生来の感の良さを発揮するのだが、それが具体的に何なのかは流石に思い当たらない。
(ま、……お兄さん関係だとは思うけど…)
傍若無人を絵に描いたような我が儘お子ちゃまに、精神的な動揺を与える存在といえば、それより他にない。
天晴れなほどに無自覚な、手の着けようの無い強烈なブラコンなのだから。
例えば、ぱっちりとした目鼻立ちのお姉さんな性格な幼なじみの事でも、少なからずの心の動きを見せるが、それすら、兄が彼女の事を憎く思ってはいない所為だろう。
要するに、兄を中心にこのひねくれ坊主の思考と行動が回っているといっても、過言ではない。無論、当人達兄弟は互いにこの事実を否定するだろうが。
「………まどろっこしいなぁ」
「あ? なんだよ、突然」
「んーん、別に。こっちの話よ。って、何してるの?」
相葉兄弟の恋愛事情とやらに想いを馳せていたカレンだったが、愛想の欠片もない同居者が何やらゴソゴソ荷物を纏めているのに、不思議そうな顔をしてみせる。
「見りゃわかんだろ」
「わかんないから聞いてるんだけど…?」
「荷物纏めてンだよ」
「何で?」
「ここを出てく」
「………………………何で?」
余りに唐突で、話が見えてこない。カレンは目を皿のようにして驚きを表すと、再び同じ問いを口にした。
「……兄貴に会ってきたからだ。
これからも会いに行く。だから、ここに厄介になるわけにはいかない」
「? って、それは何?
もしかして、共謀者としてあたしに迷惑が掛かるとか? それとも感染の問題?」
「………」
応えない。
無言が、何よりも雄弁だった。
おそらく、どちらも正解なのだろう。
感染区域に勝手に立ち入っている事実が、もし明るみにでたのなら、祐希本人は勿論、同僚であり同居者の金の少女とて在らぬ嫌疑を向けられる事は必至。
………祐希が兄に会いに行くことを知りつつ、それを止めるどころか助力を加えた事から、全くの冤罪というわけではないだろうが。
――何よりも、感染の危険が気懸かりだ。
感染源は特定されていないが、感染者との接触は確かに感染(それ)を誘発する要因たるであろう。
黒髪のエースたる少年自身は、己が決断し実行した故の結果なので、M−03に身を蝕まれようとも納得済みの事だ。
しかし、カレンは。
祐希の我が儘に巻き込まれる形となってしまう。
元々、人と群れて行動するのは不得手とする――というよりは、他人に合わせて行動しようとする気が皆無な天才様なだけに、他の人間との接触はそう心配する事はない。
向こうからも寄りつきはしないし、此方からも積極的に意志疎通をはかるつもりはないからだ。
唯一、共に過ごす時間の多い少女を除けば。
此方へ背中を向けたまま、しゃがみ込んで荷物を片づける、初恋とも呼べぬ淡い想いを一時は抱いた相手を。
その、不器用な義理堅さと優しさを。
少女は、微苦笑でもって受け止めた。
「………っ? おい?」
背なに掛かる微かな質量とぬくもりに、祐希は僅かに首をもたげて背後を窺った。
すると、丁度背中合わせのような格好で、同僚がもたれ掛かったまま、小さく呟く。
「…いなさいよ」
「………」
天賦の才を褒めそやされる少年は、闇に近い青の眼差しを戸惑いに彷徨わせた。
彼が知る『女』という生き物は、押しつけがましく、勝手気まま。すべからく行動には何らの利益を考え行動し、都合が悪ければ女である自分を強調して逃げる、狡猾なそれであるのだが。
微妙なスタンスを保って自分に接してくるカレンは、それらとはハッキリと違っていた。
女なのにドライで気安くつき合える。その分、腹の底が読めないので勝手も悪いが、基本的に嫌いなタイプじゃない。
嫌いな、人間じゃない。
「………感染ってもかよ…」
「…今更でしょ?」
「…バレたらどーすんだよ」
「その時は、巧い事して免れるから心配ご無用♪」
「すっげー、楽天的」
「ふふん、今知った? あたし、相当お気楽主義よ」
「……勝手にしろよ」
「言われなくても、勝手にするし?」
「………な」
「ッ!? わっ??」
突然、背もたれ居なくなってカレンはごろりっ、と後ろへ転がってしまった。見れば、背もたれ、もとい、ぶっきらぼうな少年はテントから出ていく所だった。
「………突然いなくなんないでよねー…」
軽く頬を染めて、少女はぼやく。
普段なら彼女自身の高い身体能力と注意力により、こんな無様な事態には陥らないのだが。去り際の一言が、未だ床と仲良くする少女から思考能力の一切を奪ったのだ。
「らーしくないの」
サンキュな。
なんて。
そんな一言で女が喜ぶとでも思ってるのだろうか、あの暴君お子さまは。
「バーか。嬉しいですよーだ。もー…、不覚ぅ」
誰も見ていないことを良いことに、そのままカレンは床でじたばたと暴れたのだった。
――――――――――――――――――――
日付変更時刻きっかり、闇に潜んで、軽やかな身のこなしをする少年が閉鎖区画の扉前まで来ていた。
前回と同じように軽やかな手つきでロックを解除し、するりと感染者区域に身を滑り潜らせる。
そして、昨夜と同じ場所で、約束の相手は小さく膝を抱えて毛布にくるまっていた。
易々とその姿を発見して、侵入者は音もなく傍らへ。
「……兄貴。来て…くれたんだな…」
隣に腰を下ろした弟に、昂冶は視線を逸らせたまま、消え入りそうなか細い声で呟く。
「…なんで…、来るんだよ。お前は……」
「…迷惑……か…?」
「――感染るって…言ってるだろ…っ」
既に多くの生徒達を死の世界へと導いた悪魔の感染症は、一度その牙に掛かれば逃れる術はない。唯一の方法といえば、感染の危険因子を可能な限り取り除くだけ事だけ。なのに、自ら進んでキャリアの元を訪れる弟の真意を、昂冶には計りかねた。
しかも――…。
ふいうち、の、……キス。
強く、抱き締められて、縋るように懐かれて。
切ない想いを、ぶつけられて。
どうしたらいいのか、わからなく、なった。
「………あにき…、ちょっとごめんな…」
「……? ゆ、うきっ?」
やけに殊勝な態度でいるVGのパイロットは、感染者という名の檻に閉じこめられたひとに、甘える仕草で擦り寄った。
身を縮めて己を守ろうとする小動物のような彼を包み込む毛布に手をかけ、するりと潜り込む。慣れた、所作。
一瞬、抵抗の意を示したものの、どうせ無駄だと諦めたのか、昂冶はまるで幼い思い出を懐かしむかのように場所を空けてやった。
半身に感じる体温と、重みが無性に心地よい。
(………昔、こういうこと…あったよな…)
一枚の毛布にくるまって互いに身を寄せ合い、夜の片隅で震えていた小さな頃。
今から思えば、大人たちも精一杯だったんだと思う。
幼い兄弟を抱えて父と別れた母。
その母も心労が重なってか、急に倒れて半月の入院生活を余儀なくされた。
祖父母はとうの昔に他界しており、頼れるのは遠い親戚だけで。
皆が、自分の事で手一杯だったから、誰も幼い子らを顧みる余裕など無かったのだ。
幼い身ながら親と引き離され、見知らぬ土地で、見知らぬ人に世話になる不安を。
無知と無垢故、理解し難き人の業を。
いきなり遠い親戚だと言われて幼児を預けられたのでは、確かに、迷惑甚だしい事であっただろう。
口にはせずとも、巧みに笑顔で隠そうとも、幼き子らの心には自然に伝わるものだ。
――…疎まれている、と。
施設の手配が済んで、どちらか一人だけなら預けられると言われた彼らは。
手間の掛からぬ『兄』の方を迷わず選択した。
少年もその選択を望んだ。
いま、この場に在るだけでも居たたまれず、身が切られるような思いを。
………大切な、大切な弟に、味あわせたくなかったから。
親戚の家に預けられてから、初めての休日。
弟の手を引いて、施設から寄越された迎えの車に乗り、一人で帰ってきた。
泣きじゃくる、彼を残して――…。
――――――――――――――――――――
「……昔さ…」
ふと、傍らでぬくもりをくれる存在が零した。
己の内に籠もり、古い思い出に浸っていた昂冶は、ゆるゆると覚醒し次の言葉を待つ。
「…こういうの……あったよな…」
「………覚えてるのか」
「流石にうろ覚えだけどよ…なんか、急に思いだした…」
「…………」
そのまま、十分ほど時が過ぎただろうか。微睡みそうになる己を叱咤しながら、茶金の髪を弟の肩に流し、昂冶は小さく囁く。
「…ホントに、感染るから……もう来ちゃダメだ…」
「俺は構わねー」
「……後先考えてモノ言ってないだろ、それ…。」
少しだけ、呆れたというニュアンスが混じる兄の台詞に、ムッとして祐希は反論した。
「本気でそう思ってるぜ、…じゃなけりゃこんなトコまで来るかよ」
「…………なぁ」
「? ンだよ、兄貴」
「お前さ、……あおいに頼まれたって言ってたろ…。様子を見てきてとか、そういうんだろ。……あいつ、心配性だし。
それならもう用件は済んだだろ…なんで、また来たんだ……?」
「………理由なら昨日言っただろ…」
「え……?」
昨日? は、あおいに頼まれたという言葉しか聞いていないはずだが。きょときょと、と、何度も空色の眼を瞬かせる兄に対し、祐希はかぁっ、と頬を染めてらしくない態度をとった。
「? ………祐希? …………………あ。」
訳も分からずにいる穏やかな性質の少年は、ふと、昨夜の事態を思い起こして……隣合う弟につられるようにして赤くなった。
――――――――――――――――――――
『………………きだっ…』
――――――――――――――――――――
妙に気恥ずかしいというか、落ち着かないというか。
互いに、変に意識してしまって、会話が続かない。
だが、法を犯して手に入れた逢瀬の時間を、沈黙で失うのは惜しい。
リヴァイアスの随一の無法者にて、天才の誉れ高き少年は、一大決心の下、己の逆送癖を必至で抑え込んだ。
――…素直に、気持ちを言葉にして表す事なんて。
酷く久しくて、巧く、優しい気遣うような台詞が出てこない。
「……俺が、兄貴に逢いたかったから来たんだ」
「………」
「兄貴に、逢いたかった…」
「………」
昂冶は、反論するでもなく相槌を打つわけでもなく、ただ、その綺麗な眼差しを閉ざして、弟の癖の強い声に心を浸していた。
無反応でいてくれたのは、逆に祐希には有り難かった。
まるで、一人で独白しているような心持ちでいられたので、妙に焦って慌てる事がない。
「…俺の前から、いなくなるなよ……」
「………」
「兄貴が…いないと不安なんだ…」
「………」
「兄貴――、……………好き……だ…」
――――――――――――――――――――
壊れたままデモ ずっと 傍に イテ
――――――――――――――――――――
傍若無人、無愛想の仏頂面、のくせに、天より与えられた才気を如何なく発揮するエースパイロットが、愛しい兄(ひと)の元へ通い初めてから、平穏のままに一週間が過ぎようとしていた。
「なーに? この頃、機嫌いいじゃない」
VGのコックピットで作業に没頭する同僚を揶揄ってカレンが言った。
既にリフト鑑には人気はなく、彼ら、パイロットだけが遅くまでソリッドの微調整を行っていたのだが。
片手でシートを溶かして作ったインスタントの珈琲を差し出しながら、少女は微笑む。
こんなものでも、物資難の現在では貴重な嗜好品なので、祐希は黙って受け取り、まぁな、と短く返答した。
それだけで、彼が普段よりも遙かに上機嫌だということが窺えて、ふぅん? と、金の髪の少女は嬉しそうにした。
「ねぇ」
「…なんだよ?」
手元の珈琲の熱さに眉を潜めながら、律儀に同僚は答える。
すると、人目を憚る事なのか、カレンはひょいと屈んで祐希の耳元へと唇を寄せた。
(もうチューくらい済ませた?)
「ぐふっ!? がふっ、げふげふっ!!」
「ちょっ、何よもー」
珈琲に思いっきり咽せて咳き込む祐希に、カレンは非難がましい声を上げる。
「全く…、折角いいものあげようと思ったのに」
「………だっ、ッまえ、何いっ…」
呼吸がままならず、息苦しさに眦に涙を浮かべる黒髪の少年は、事の元凶であるパイロット仲間を思いっきり睨みあげた。
「ふーん? その調子だとチュー位は進んでるみたいね」
どことなく嬉しそうなカレンに、最早何事か申し立てる気力もなく、祐希は大きな世話だッ、と噛み付いた。
「いっちいち、首ツッこんでくんじゃねーよッ! ほってお……?」
鼻先に押しつけられるようにして差し出されたピンク色の可愛らしい容器。プラスチック製のそれは、市販されるハンドクリームの類に類似していた。
「――…ンだよ、これ」
「ローションよ。ローションっ。
ちゃんと準備してあげないと辛いんだから」
「………準備、って…」
とりあえずカレンから容器を受け取り、困惑する天才少年。すると、同部署を勤める少女は魔女のように微笑んで見せた。
「とーぼけちゃって♪
ちなみにそれ、ちょっとした催淫効果もあるから巧く使ってね」
「!」
言うだけ言って立ち去る気紛れな同僚の、その後ろ姿を見送りながら、彼女が示唆していた『事』を正しく理解して、赤い顔のまま固まるエースパイロット。
自分自身でも呆れ果てるほどの純情ぶりだとは思うが、その、行為について全く微塵も考えが及んでいなかった。
傍にいて、鼓動を感じて、それだけで幸福なんて、陳腐な事。
本気で思っていた。
けれど、気付いてしまったからには手遅れだ。
一度火がついた感情は、やがて劣情と名を変えて胸の内に燻り続ける。
「………」
黒の戦艦の権力者が一人、相葉祐希は、ぎゅっ、と、掌に収められた薬を無言で握りしめた……。
――――――――――――――――――――
「…兄貴」
既に、慣習となった逢瀬。
吐息だけで愛しい人の名を呼ぶと、僅かに疲労の色を濃くした空色の眼を笑みの形にして向けてくれる。
「祐希……」
けれど、兄の浮かべる微笑みはいつも寂しさに歪められてしまっていた。
そっと毛布の端を持ち上げて手招きする、そんな仕草に誘われ、祐希は昂冶の隣に潜り込んだ。
「なぁ、兄貴。いっつも抜けてきてるけど、平気なのかよ」
「ん? ああ、大丈夫。
みんな寝てるし、それに…部屋から出ようとしないから。他人(ひと)の事にも凄く無関心だしさ」
「…ま、そーだよな」
救いの光の無い逃亡生活の果て、謎の病魔に命の期限を突きつけられ、更に社交的でいられる者などそうはいるまい。
考えてみれば至極当然の有り様だ。
兄の説明に得心する整った横顔。乱雑と後ろで束ねられた黒髪の一筋が零れて、ドキリとさせられる。、そんな弟に昂冶は質問した。
「お前の方は大丈夫なのか?」
「何が?」
「何が、って…、ホントはこういうことしちゃいけないだろ。見つかったりとか…」
「まァな。けど、心配することねーよ。ここの警備、外部からのアクセスには甘いしな」
「…ならいいけど……」
一級品なのは、口と性格の悪さだけではない。
同じ毛布にくるまって隣り合っている黒髪の少年は、天才の名を冠する技量を持つのだ。彼が『大丈夫』と言うのならそうなのだろう。
「………肩、貸してな」
と、重心を掛けてくる兄。見れば、頭を肩に寄っかからせて昂冶が瞼を下ろしていた。
「ちゃんと返せよ」
なんて憎まれ口をたたいてみせると、ふっ、と優しい風貌の少年が吹き出す。
「どうやって返すんだよ?」
「………キス一回」
「…ばーか」
微かに頬を染めて、咎めるように睨み上げてくる表情が、やけに扇情的。
どくんっ、と、心が熱くなる。
「……な、兄貴」
「ん?」
「俺、兄貴が好きだっていったよな」
「……うん」
恥ずかしげに空色の眼差しを伏せる。
「兄貴は?」
「……………すき、だよ」
消え入りそうな微かな声で応えてくれる、綺麗な人。
愛おしさに胸が詰まり、そうっと、口唇をあわせていた。
薄い毛布にくるまり何時も自分を待っていてくれる兄のそれは、ひんやりとした冷たさと微かな緊張を伝えていた。
もう、何度目かになる、キス。
「……こういう意味、だよな?」
「……ん」
「なぁ、……いいか?」
「?」
何が? と、無垢な表情でいる兄の額に触れるだけの口づけをおとし、
「これの先」
囁けば、かーっ、と、見事なまでの朱色に染まる横顔。
「…………そっ、れって」
「……ダメ、か…?」
普段の、思いやりの一片すら無い傍若無人っぷりとはかけ離れ、臆病になって、確認する天下のエースパイロット。
その、真摯で揺らぎない漆黒の眼に射すくめられて、吐息(いき)すら、絡め取られる錯覚。
「………祐希…」
「ん?」
「目、瞑って…て」
「……ああ。」
言われたとおりに、瞼の裏に迷いのない黒の珠玉を閉じこめる弟の暖かい唇に、恐る恐る、昂冶は自分のものを合わせたのだった…。
――――――――――――――――――――
壊れた ニンギョウ を 愛して
――――――――――――――――――――