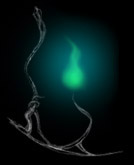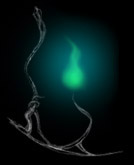傍へ――、鼓動を感じさせて、
傀
儡
第五話
あなたは 、まるでニンギョウのよう
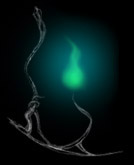
いとし キミ よ
――――――――――――――――――――
果て無き宇宙の深淵にて、ただ、寄る辺無く漂い続ける子どもたちの王国。
恐怖と非業と絶望で、指先すら繰り糸に絡め取られ自由を繋がれた人形たちの楽園。
狂気に咲く華は、常夜に美しい。
――――――――――――――――――――
「…チッ」
特にVGによる戦闘スキルに一群を抜いた活躍を見せる少年は、酷く苛立っていた。
心情的には隔離区域に捕えられた兄の元に毎日でも会いに行きたいが、流石に、そういう訳にはいかない。
VGとしての責務や雑務に追われて足を運べない日もあるが――感染者区域に踏み込むのは、最大の禁忌。艦内の非感染者全てに対する裏切り行為だ。個人主義の少年にとって、有象無象からの誹謗の声など、取るに足らぬ些事に過ぎぬが、その矛先が愛しき存在へ向いてしまうのは本意では無い。
「なーに? イライラしちゃって」
同じテントで生活スペースを共にする利発な少女が、ギガプレイヤーを指先で操作しながら、ひょいと肩を竦める。
「ウルセェ、テメェにゃ関係ねーだろ」
「まぁねー。さ、て…と」
ピ、という小さな電子音の後に、少女――VGの優秀なパイロットでもあるカレンは立ち上がった。んー、と大きく背伸びをしてみせて、不貞腐れた様子で仰向けに寝転がる居候に向き直った。そして、死海の青さを思わせる瞳を一瞬だけ翳らせる。
「…ねぇ」
「ンだよ」
愛しい人との逢瀬すら思うようにいかず荒れる少年は、寂しげな少女の変化には、気付かない。いや、万が一ここで察していたからといって、結果が違っていたとは限らないが。
「――なんでもない。それじゃ、ね」
にっこりと。
ヘリクリサムの花のように明るく微笑んで見せた少女は、それから丸一日経っても戻っては来なかった。
――――――――――――――――――――
まるで巨大な棺のような戦艦は、死の匂いと気配に満ち満ちて、宇宙を行く。
行く末に希望など見出せぬ旅路だと、皆が、迫り来る運命を感じ取りながらも。
それでも、前へ進むのは何のためなのだろうか。
その意味も、意義も、目的も、全ての指針を失った艦(ふね)は、星の海を漂いながら、運命の波間で、ひたすらにもがいていた。
人目を忍んで――いや、現在の黒の戦艦リヴァイアスに於いては、『そう』する必要も無いのだが――周囲を警戒しながら、才気溢れる荒削りな魅力の少年は、隔離区域へと足を運んでいた。
入り口の電子ロックは、今日も呆気無く解除され、易々と外部からの進入を受け入れた。
この背徳の行為は、狂気の独裁者として君臨する尾瀬に見咎められており、セキュリティシステムに何らかの対抗策を打ち出してくると予測していただけに、肩透かしを食らった気分でもある。
――邪魔をされないというのは、此方としても歓迎すべき状況ではあるのだが、気に食わない。己が思想に同調せぬ『敵』を徹底して排除する危険思想の持ち主が、こうも大人しく事態を見守る訳が無いのだ。また、同居人の少女がテントに戻って来ていない事も気懸かりではあった。
(まぁ…、あの女ならどーとでもするだろーけどな)
機転も度胸も腕っ節も、並みの女とは比べるべくも無い。どのような状況に陥ろうとも、したたに世の中を渡っていくだけの度量の持ち主である、金髪のソバージュの少女の姿を思い出し、比べれば、余程兄のが心配だと、無意識に早足になる。
「兄貴」
何時ものように、無造作に散ばるコンテナの影で、古い毛布に頭から包まる兄の姿を見つけ、祐希は心よりの安堵を覚えた。
「…ゆうき…」
厚い布地の下から不安そうに、けれど愛しそうに。震えながら伺ってくる瞳は、今となっては二度と戻れぬやもしれぬ、懐かしき故郷の紺碧の空を思い起こさせる。
「体調、良くねェのか?」
小さく膝を抱える兄の傍に物音をさせないよう腰を下ろし、黒の王国でも、その無法さと実力の高さで名を馳せる少年は、無造作に訊いた。
「…ん、大丈夫だよ。そりゃ、元気とも言えないけどさ」
「……無理すんなよ? 前より痩せてんじゃねぇのか?」
「元々こんなモンだよ。祐希は心配し過ぎ」
弱々しく微笑んで見せる姿が、ただの強がりに過ぎない事は一目瞭然だ。胸を掻き毟られる程の不安に、祐希は居た堪れない心地となる。
「――…兄貴」
「…ん?」
呼べば、所在無さ気なそれではあるが、確かに応える声――存在。
触れれば、温かい。
そんな『当たり前』が、ボロボロと、剥がれ落ちてゆく、今。
最期に、この手の中に残るのは一体何なのか――…。
「…地球に戻ったら、部屋の仕切り外そうな」
そっと、腫れ物を扱うように肩を抱けば、その骨ばかりの薄い肉の感触に、喉が震えた。
「……プライバシーの侵害だと思うけど?」
素直に肩口に頭を預けてくるのが愛おしい。絹のような滑らかな指どおりの茶金の髪が、サラサラと流れて落ちるのに、口唇を寄せた。
「いーんだよ…、兄貴は全部俺のだ――…」
「…仕方ないなぁ」
劣情の伴わぬ、懐いたペットが主人にじゃれるような悪戯な愛撫に、擽ったそうに身を捩りながら、昂治は忍び笑いを漏らした。
「仕切りを外したら、部屋の片付けしないとな」
「…ンでだよ、必要ねーだろ」
家事全般が絶望的に苦手な仕方の無い弟が、不服そうに反論してくるのを、昂治はピシャリと嗜めた。
「お前の方は、足の踏み場も無いほど散らかってただろ? 俺は汚いのは嫌だからな?
後、ベッドの下の本、隠し場所変えたほうがいいぞ? あんなトコじゃバレバレだぞ」
「!! ちょ、っと待てよ!! なんで兄貴がソレを知ってンだッ…!?」
健康な青少年の部屋のベッドの下――と言えば、お決まりだろう。所謂、エロ本の類だ。何処からそういった類のモノを手に入れたのかは不明だが、早熟な少年はアダルト雑誌を隠し持っていた。
指摘に飛び跳ねる程驚いた様子の弟に、昂治は己の中の『兄』としての部分を甚く満感させた。身体的にも能力的にも、幼い頃から立場を逆転させてしまった弟に、一矢報いたような気分だ。
「ベタ過ぎだもん。俺じゃなくってもバレるぞ」
「…じゃ、なくってッ…!」
今となっては取るに足らぬ確執も障害も乗り越えて恋仲となった最愛の人だが、ここに至るまでといえば、決して兄弟仲は良い方では無く、険悪と言い換えても良い位だったのだ。それこそ、お互いの存在を無視しあい、その領域に足を踏み入れるなど以ての外。確かにベッドの下のは隠し場所としてはベタだが、それに気付くには、いがみ合っている弟の境界を踏み越えなければならないのだ。
「…部屋、なんて。何時の間に――…」
「――…念の為言っておくけど、お前の部屋で家捜しなんて悪趣味な真似してないからな。
そっち側の部屋を通り抜ける時に、雑誌…だったかな? 何かに足を引っ掛けて転んだんだよ。で、ベッドの下に何か隠してるのが見えてさ」
「…ガキじゃあるまいし、なんで部屋ですっころンでんだよ。アンタは」
事の顛末を聞かされて気が抜けたらしい祐希は、はぁ、と盛大に溜息を吐いて肩の力を抜いた。ギ、と寄りかかられたコンテナが小さく軋む。
「…悪かったな。だから、片付けてくれって言ってるだろっ…」
頭から覆う毛布の中で剥れる横顔が愛おしい。こんな可愛らしいモノが自分の所有物なのかと改め実感して、幸福感に包まれた。好きだと認めてしまえば、もう何も想いを縛るものは無い。痩せた肩に回した腕に力を籠めれば、どうかしたのかと、故郷の空を映した穏やかな双眸で見上げられた。
「わーっかったよ、兄貴。帰ったらちゃんと片付ける。雑誌も全部捨てる。
それでいいだろ?」
「え?」
予測以上の回答に、今度は昂治が面食らう番だった。困ったように眉を下げる姿が犯罪的に愛らしい。こんなにも大切な存在を自ら手放した、過去の己の不甲斐無さを腹立たしく思いながらも、祐希は、文句でもあるのか? と、返した。
「文句じゃないけど、別に捨てるまでしなくても――…、ンッ?」
いいんじゃないか、と言い掛けた言葉は遮られて、愛おしみ啄むだけの接吻に、己の内に巣食う病魔の存在をも一瞬彼方へ忘れ、酔い痴れた。
「……ゆう、き」
精魂尽き果てるまで身体を重ね、肉欲のまま全てを奪い去る嵐のような行為とは違い、恵みの雨のように、ただひたすらに与えられる愛。降り注ぐ優しさと愛しさに、胸が潰れそうだった。今、ここに共にあるだけで――ともすれば罪深い己が傲慢を自覚しながら。それでも、抱き寄せられる腕を振り払う事など…、可能ならば、とうにこの幸福は失われているのだろう。
「いーんだよ、別に。あんな本なんか無くても、兄貴が相手してくれるんだろ?」
「……? 何を……?」
無尽蔵の愛に包まれて、恍惚の表情でいる兄の頬に、殊更大きな音を立てて吸い付いて、そのまま耳朶に熱い吐息と共に囁きを吹き込んだ。
「…セックス」
「ッ! ばっ…!! っ……ン」
余りの露骨な物言いに病的な白さの膚に、一瞬で赤みが挿す。抗議の意味合いで開きかけた口唇は深く合わされ、逃げを打つ舌を優しく絡み取られて、病魔に身を冒される少年は、必死で蹂躙者の胸に縋り付いた。
「……兄貴…」
嬲りつくした口唇は、唾液に濡れぷくりと紅い。その視覚を襲う淫らさに、若さを持て余す少年は、血が激しく脈打つのを感じた。
「ん…、ゆーきの…ばか…」
激しい接吻に息も絶え絶えになりながら、可愛らしく非難する兄に、傍若無人の限りを尽くす弟は、まるで借りて来た猫のように大人しく、しおらしい。
「ゴメン。…でも…、好きだ…」
「――…ん。俺も」
「……好きだ――…」
堪らず――、コンテナから上半身を起こし、全身で華奢な肢体を抱き締めた。厚手の毛布の上からでも感じられる肩の冷たさと、震え。それは最早、人の力ではどうしようも無い――圧倒的なモノ。
「…なんだよ、随分甘えて…。子どもみたいだぞ…?」
「いいだろ…、アンタよりガキなんだし…」
抱き寄せる腕の力強さに心を寄せながら、病の影を色濃くする少年は、偲び笑いを零す。拗ねた口調で必死に抱きついてくる姿は、とても黒の王国を護る騎士――AGの天才パイロットとは思えない。これでは、孤独に怯え温もりを欲しがるばかりの、ただの子どもだ。
――そう、子ども。
(……俺は…、)
黒の戦艦リヴァイアスの行く末には未来など無いと、全ての子らが己の不遇を呪い、運命に唾棄している中で、何故か今日明日も知れぬ少年の心は静かに凪いでいた。
妙な確信が――あるのだ。
死と生の狭間に置かれた若者達の青春群像を描く陳腐な舞台を、何処か、遠い場所から見下ろしているような奇妙な達観。
その中で『相葉祐希』という役柄は、このまま死亡して物語は幕を引くのだろうと、冷静に続きを追う自身を自覚していた。
「兄貴…」
「ん?」
愛しき人の横顔に、逢瀬を繰り返す程に色を増す死相の翳り。ヒタヒタと迫り来るのは、終焉という名の隣人、その息吹。闇はそう遠くない未来に、全ての『生命』を屠るだろう。
「…好きだ……」
どうすればこの温もりをこのまま留め置けるのだろうか、そんな埒も明かない事ばかり考えては思考は四隅から、ハラハラと剥がれ落ちてゆく。
胸を締め付けられるような幸福感の中で、世界は、抗う術も無く時を刻んでいた。
――――――――――――――――――――
謎の死病――感染症【M-03】による被害で黒の戦艦の人口は、最盛期の半分、以下。
感染経路の特定が困難であるため、発病者はもとより感染者も、隔離区域に纏めて閉じ込められる。既に病魔に倒れ臥し、命を落とした子ども等の数も相当数にのぼっており、リヴァイアスは生者の絶望と死者の嘆きが渦巻く、死の艦と成り果てていた。
よもや、救いの可能性など誰もが露ほども考えはしまいが、それでも――、
『かえり、タい…』
突如――そう、余りにも突然に呟かれた言葉に、人気の無い通路を一人歩んでいた赤のジャケットの人物は、不審気に周囲を穿った。端整な容貌の中に粗野な魅力が光る少年――相葉裕希は、気配を追って険しい目付きでなんなく『それ』を認めた。
(……女?)
メタリックピンクの金属のような質感の服装と帽子、という一見奇抜な装いが良く似合う少女が、ぼんやりと虚空を見つめていた。空中交差通路の最も上段にある通路にいるため、随分と遠目になり、ハッキリとは分からないが、可憐な――美少女と言い換えても良いだろう女生徒だ。
リーヴェ・デルタで見かけたことは無いが、この得体の知れぬ艦に元々の乗船者が存在していたとは考えにくい。おそらく、同じ学び舎の者には違いない。声は、直ぐ傍――切ない程の距離から降り注いだように思われたが、ただの思い過ごしだろうと不審な少女から視線を逸らし――、
『か、えり…タイ…?』
眼前の光景に、絶句、した。
「……カ、レン…?」
『それ』が現実で無い事は明白だった。
ふわりと宙を舞う波を描く金髪は、彼女の歩みに合わせて、サラサラと揺れる。足取りは静かで、ゆったりと、惑う事無く、中空を進んでいた。触れられる距離にありながら、決して手を伸ばせない。受け入れがたい状況に、心の中の冷静な場所が、『コレ』が一日前、彼女と別れた後の映像である事を理解していた。
「…何処に…?」
怪訝そうに行き先を見つめる祐希を、決して彼女は認めてはいないだろう。しかし、利発な少女はくるりと振り返り、哀しみだけを湛えた深い蒼の瞳で弱々しい微笑を象った。
『ねぇ、……アナタ、この艦の何?』
瞳は言葉を求め真直ぐに前を――少し、上に視線をやっているようだった。
『…そう、まぁ、何でもいいわ。
でも、アナタはリーヴェ・デルタの生徒じゃないでしょ?
何処からやってきたの?』
最早、先程までの必死さは無い。答えを諦めているようにも見えた。
(――カレンのヤツ、誰と話をしてやがるんだ…?)
この狭い王国の中でまるで幻のように行方を眩ました少女は、確かに『誰か』と話しているようだった。しかし、様子から察するに『誰か』は、彼女の求める言葉を正しく理解せずに、答えは望むものではないようだった。
『え? 私? ――秘密よ。謎の女、なんてカッコ良くない?』
おどけてみせる姿は、普段と何ら変わる事も無く。
それが逆に、彼女の失踪に現実味を帯びさせる。
この後、少女は行方を眩ますのだと、天啓の如く確信は強く。
『私ね、死んじゃうのよ』
不意に話題が変わる。それは核心を突く告白だった。
『何故って…、そうね――巡り合わせ、かしらね』
誰かから視線を逸らし、少女は寂しそうに漏らした。死の恐怖に脅える素振りすら無く、ただ、彼女は悲しみの感情に魂を震わせていた。
『……おかしな事を訊くのね。
死にたい人間なんて――稀にしかいないんじゃないかしら。
――…、そうね。あんな場所、二度と戻るものかって…そう思ったけど。
でも、最期に一度くらい見納めておけば良かったかもね』
くるりと背中を向ける少女の幻影に、時空を越えた場所からの、ただの傍観者でしかない少年は、咄嗟に腕を伸ばした。
「カレン!!」
思わず叫んだ言葉は、静寂の中に木霊すだけで。決して過去を生きる彼女に届きはしない。しかし、少女は――ピクリと肩を揺らして背後を窺った。
『…何か、今――?』
「! おい! カレン!! 行くな!! 戻って来い、バカ!!!」
『…気のせいね。今頃、あのブラコンはお兄ちゃんとラブラブだし』
ひょいと肩を竦め、闇に鮮やかな輝きを残し、金髪の少女は遠ざかる。もう――声は二度と届かないのだろう。何故なら、事実、彼女はそのまま消えたのだから。
激しい無力感に苛まれ、天才の名を欲しいままにするVGを操縦者は、柵に背中を凭れさせながら、狭くて暗い灰色の天井を見上げた。そのまま膝を折り、乾いた笑いが零れる。
「…分かってた、はずだ」
聡明で機知に富んだ性格の少女が、如何な苦境とは言え、自ら生命を絶つ行動に出るとは考え難い。ならば、行為の原因は唯一つしか有り得ない。王国を蝕む病魔。子ども等の希望も未来も打ち砕く最果ての悪魔。
「……M-03…」
最早、幕引きを待つのみの舞台ならば、いっそこの手で壊してしまおうか。
そうすれば、別れに怯えなくて済む。喪失を嘆かなくて済む。痛みを抱えて明日を迎えずに済む。あの優しく残酷な恋人は、決して死を望む事を赦してはくれないだろうから。約束を求められる前に、愛を永遠に成就させてしまおうか。
「……愛してる、兄貴……」
苦しまないように逝かせるには何が一番効果的なのだろうか。
絞殺は苦しむだろうし、刺殺も痛みがある、撲殺などとんでもない。こうして考えると、優しく殺す方法というのは、そうそう見つかるものでは無いと実感する。いっそ、犯り殺してしまおうか。体力の覚束無い今の状況なら、それも可能だろう。精魂尽き果てるまで抱いて、犯して、そうやって心臓がゆっくりと、動かなくなるまで――、
「ッ…!!」
ブルリ、と全身に悪寒が奔り、甘い陶酔に耽っていた少年は、バッと顔を上げた。
「…なに、考えてンだよッ…、俺は!!」
憤る感情に任せて柵に打ち付けた拳は、確かに痛みを訴えていたものの。胸の奥から這い出る信じ難い醜悪な欲望は、愛に満ちる幸福な記憶と想いを内側から喰らってゆく。甘美な悪夢から逃れようと、拙い抵抗は、ただ己が身を苦悶についやした。
――――――――――――――――――――
「……今日は、祐希のヤツ来ないだろうな…」
金茶色の髪の少年は痩せ細った自身の腕に溜息を零し、何時もの約束の場所でコンテナを背に、毛布の中で膝を抱えていた。
食料が充分に行渡っていない現状ではあるが、それでも死亡者の多さから、日々の糧に困窮する程では無い。単純に食欲が湧かないのだ。食べなければ痩せる。明快な事実だ。
「惨めだよな。ホントに…」
こんな、情けない姿になってまで、それでも生きていたいと願う。己の欲望の深さには呆れ果てるばかりだ。少し前まではクルーとして雑務をこなし、多少なりとも役立っていたのだろうが、今やただの艦のお荷物。更に言うならば、リヴァイアスの戦闘の要、実の弟である少年との逢瀬を重ねる事で、大切なVGのパイロットを感染の危機に晒し続けるという王国への裏切りを自覚しながら、その腕を、愛を、求めてしまう。
失いたくない。傍にいて欲しい。けれど、そう願い請う事が如何に罪深く愚かであるのかを、理解して――いながら、それでも――。
「………」
暫く、必要な肉まで削げ落ちた己の腕を見つめていた昂治は、不意に指折り何かを数え始めた。
「…地球(ホーム)に戻ったら、部屋を片付けて、布団を干して、買い物に出掛けて…」
特別なことなど、何一つ無い。
ただ、今までも繰り返していた日常を、取り戻すだけ。
「夕飯に、……好きなものを…作って…」
不必要に豪華で無くていい。毎日何気なく口にしていた、家庭料理が食卓に並ぶだけで充分だ。
「――風呂に、はい、……」
それから、たっぷりの水で疲れを癒して、部屋のベッドで休もう。
「………ッ…」
――声が、震えた。
抱えた脚を更に小さく纏め膝に額を押し付けると、死病に侵される少年は、じっと何かに耐え忍ぶように息を押し殺した。
滅びの洗礼を生き延びたオトナ達が必死で作り上げた箱庭の中、優しい平和に窮屈で退屈だと不満を漏らし、甘え生きてきた。それ自体は悪ではあるまい。幸運な時代に巡り合わせた子等の、相応の権利というものだ。
飽く事無く繰り返される日々、今日も明日も明後日も、同じ時間が廻ってゆくものだと確信していた。それらは当然のように傍に在りすぎて、無力な時代の子等はただ与えられるだけの恩恵に浸り、自身の指針を定める事すら適わない。
「……帰りたい……」
無意識に口をついた小さな願いは、想い出の中で色褪せず輝く故郷の青空に融けてゆく。記憶に残る幸福の群像は彼方へ遠ざかり、不遇の子等の泣き濡れる瞳では、世界はその輪郭を滲ませるばかりだ。
「帰れるさ」
「――…え…」
不意の宣告は、頭上から。
それは決して光ではなく、希望ではなく、未来ではなく。
ただ、世界が壊れる音を聴いた。
――――――――――――――――――――
永劫なる星の海原を孤独のまま漂流し続ける、無二の戦艦リヴァイアス。
今、この艦に於いて『彼』の名を知らぬ者などいるはずもない、滅びゆく王国の支配者――独裁の狂王。天高く掲げた理想故、自らの信念に由る修羅覇道を貫く孤高の存在。
「…尾瀬……?」
昨日の今日だった。
流石に立ち入り禁止区域に連日入り浸っていては悪目立ちする。その為、逸る気持ちを抑え、二日に一度程程のペースで兄との逢瀬を繰り返していたが、時間軸を曲げた昨夜の不可思な体験にて不吉な予感を覚えていたのだ。
約束があろうがなかろうが、同じ場所同じ刻限に常に兄の姿はあり。くすんだ色の毛布に包まり、昏々と眠り込んでいる様子の兄が、不意に此方の気配に気付き、嬉しそうに微笑む瞬間がとても好きだった――、
「なんだ。…昂治との約束は明日だとばかり思ってたのに。今日も来たんだな」
狂気は、甘く優しく、諭すように囁いた。
「あ…、にき……?」
コンテナに凭れたまま、毛布の裾から覗く床に投げ出され指は、ぴくりとも動かない大切な人の名を――呼ぶ。心臓がまるで脳の裏側で直接に拍動するようだった。大きすぎる鼓動、不規則な呼吸。静寂だけが支配する世界で、慟哭は声にならず、嘆傷は咽を抉る。
「どうせなら、もう少し早く来るべきだったな」
右手にしたままの血塗れたナイフを無造作に翳し、彼は淡々と告げた。抑揚も感情も無い、ただ無味乾燥に事実だけを告げる響きに――如何な横暴を繰り返し、悪道に堕ちようとも、最後に残り失われることの無い、母なる地球の優しい命の器が、軋んだ。
「もう、――間に合わない」
何が起こっているのか、どうすればいいのか。
光景が割れた鏡の破片のように、次々と視界に突き刺さる。
それは、端的過ぎて――現実を認識するだけの情報に至らない。
「手遅れだよ。祐希」
何時の間にか正面にまで近づいていた尾瀬は、瞳孔を大きく開き、呆然と立ち竦む少年の胸に兇器を押し付けた。咄嗟に腕は動き、鈍い輝きのそれは己の掌に収まる。
「………」
視界を大きく遮る位置にいた狂気の王が間近に迫った事で、目の前が開ける。
古ぼけた毛布は――紅く、重く、世界は、闇に染まる。
「…、………」
唯一無二の肉親でもある大切な恋人(は、肩口からの夥しい鮮血に完全に力を失い、ただ壊れた人形のように四肢を投げ出していた。その全身が物悲しいまでにそぼ濡れており、とても説明のつかない――血が……流れていた。
「――…な、…んで…」
陳腐過ぎる台詞が口が零れ落ちる。
分かりきった、事だ。
今更、何故と答えを求めるまでも無い。
こんな馬鹿げた場面に、余りに似合いなとぼけた問いかけに、正気と狂気の狭間で無残に裂かれた人格を、不器用な継ぎ接ぎで繋ぎ合わせる危うき黒の王は、絶対的に欠けた微笑みを浮かべる。
「――単純な理由だよ、祐希。
一つ、VGのパイロットに欠員が出た。二つ、これ以上貴重な戦力を失うわけにはいかない。三つ、だから、強攻策に出た。それだけだ」
「――……」
果てし無い絶望は奈落の心地で黒髪の少年の頬を撫で、突然の喪失に闇空の瞳は、酷く脅えて――、動揺の余りに焦点すら合わないまま。
「それだけなんだ。祐希」
蕩ける甘さの残酷な響きに――、
未だ幼い黒豹は、自身すら呑み込む程に巨大に膨れ上がった憎悪の牙を剥く。
人が死ぬ事など、案外に単純で簡単なのだと。
刃を引き抜く生々しい感触に、ひとつ、嗤った。
――――――――――――――――――――
――生気の失せた頬は青白く、触れる指先からは、ただ温度が奪われる。
肩口を深く抉る傷跡は、鼓動を止めても尚、痛々しく鮮やかな鮮血に染まっていた。
余りの膚の白さと無機質さに、精巧な人形かと紛う程、死相は美しい。
「あに…き」
血糊を浴び赤銅色に反射する刃は、力も無く、ただ指の間から滑り落ちた。
膝を折り、そっと腫れ物に触れるように冷たい躯を抱き締めた。
――…かなしい、器。
愛しい人の、魂の、抜け殻。
「………」
己が浅慮を悔いればキリは無く、埒も明かない。
ただ――、二度と。
この先に進み往こうとも、決して。
あの空色の瞳には逢えないのだと。
それだけが、確かな真実。
変わらない、残酷な現実。
「……あにき…、…」
紡ぐ麗しき愛の言葉は、恵みなく干からびて、受け手も無く次々と床に零れる。
痛みは――最早、感じない。
ただ、愛しき人を永劫の闇に喪った少年は、虚ろなままで――、
「………」
無造作にある床のナイフを、手探りで、拾い上げた。
左の指が、無意識に心臓の上を辿り、位置を確かめた。
「……すきだ…」
――――――――――――――――――――
全ての惨劇の幕が引かれ、薄藤の髪と透き通る肌が可憐に美しい神秘の少女は、表情も無く場に降り立った。
コクン、と小首を傾げ、意思の無い虚ろな器達を見渡す。
誰かの叫びが届いたのだ。悲痛な、最期の願い。
生きたい、という生物の本能的なそれではなく。
愛し人に、どうか――
『幸、多かれ』
外見を裏切らぬ愛らしい声が、波紋となって、静寂を揺らし。
黒のリヴァイアスの心を宿し子ども等を護る存在の、その無垢たる瞳を、濡らした。
――――――――――――――――――――
もう ダレ、も ウゴカな い
――――――――――――――――――――