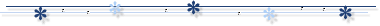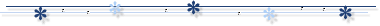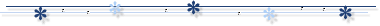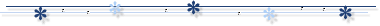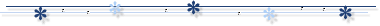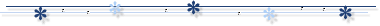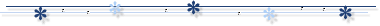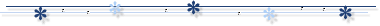空の世界
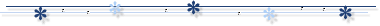
ヴァイタル・ガーターから見放さた絶望に、誰も彼もが恐怖に足をすくわれる中。400余名の子ども達を抱え漂流するリヴァイアスで、ただ一人。彼は、蒼色の獣は、己が牙を自身へと突きつけていた。
ブリッジで脅える全てのクルーが正面のスクリーンに集中する場面で。相葉昴治は、オペレーターの任を受け持つ優しい風貌の彼は、気高き生き様を見せつける孤高の獣に、圧倒され魅入ってしまった。
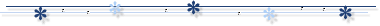
未曾有の危機を乗り越え、リヴァイアスは一時の安息を得ていた。
ピンガーの反応を確かめる役目の人間の他には、ブリッジにも誰もおらず、全ての人間が死へと直面した緊張と生き延びた喜びで、深い眠りについていた。
静寂の中で、その人影は足音も高く通路を、リフト艦へと移動していた。
すらりと伸びた体躯に、蒼の印象の強い、凛々しき少年。
現在、黒のヴァイア艦リヴァイアスを支配する王者、エアーズ・ブルー、その人物だ。
「……?」
ふと、少年は何かを目端に捕らえて、表情を微かに険しくした。
そう。何かが、通路の端で蹲っていたのだ。
現在のリヴァイアスはまさに無防備状態だ。そこを狙っての、敵の侵入かと、注意深く彼はそれへ近づいた。が、目的の正体を見極めて、ブルーは己の杞憂をあざけった。
「あれ、ブルー?」
その場所にいたのは、ブリッジ・クルーに自分が指名した可愛らしい顔立ちが目を引く少年だったからだ。
くりっとした眼に、小柄で頼りない体つき。極め付きが、相手に警戒を与えないのほほんとした雰囲気だ。これで一つ年上なのだから、信じがたい。
「……何をしている」
「あ、あははは。ちょっとくじいちゃって、動けないんだ」
「くじいいた…? こんな何もない所でつまづきでもしたのか、器用なヤツだ」
「はは、ブルーはなんでここに?」
「俺が何処にいようが、勝手だ」
ぴしゃりとはね除ける態度にも、昴治はそうだね、と微笑んだだけで、ひるむ素振りすらない。
変わった人間だと、何時も、そう感じるのだ。
相葉昴治という少年は、ブルーが今まで出会ったどんな人間とも違っていた。一見、酷く頼りないただの平凡な少年なのだが、何か違っているのだ。その正体はわからないが、とりあえずそんな昴治を気に入っている自分自身の気持ちだけは、はっきりとしていた。
「IDカードは持ってないのか?」
「え? あ、ううん。持ってるよ、ほら」
のんびりと応える昴治に、ブルーは呆れ果てた。
「ならそれで誰かに連絡をすればいいだろう、このままずっと、こうしているつもりか」
ぶっきらぼうな態度と言葉でも、それが心配してくれているのだと昴治には伝わったようだ。伊達に長年ひねくれ坊主の兄をしていないということなのだろう。普段は、ぼーっとしているくせに、妙に聡かったりする。
「でもほら、今、みんな疲れてるだろ。だから、呼び出すのも悪いかなぁって。
一人で医務室まで行けないこともないし。痛みが収まってから歩いていこうと思ってるんだけど…、まだちょっと痛くてさ」
平気だから、ありがとう。
そう言って、痛みを堪えて立ち上がろうとする昴治の細腰をブルーは片手で引き寄せた。
「!? わ、なにっ? ブルー??」
「無理をすれば癖になる…、掴まっていろ」
淡々とした命令口調でブルーはさっと昴治を横抱きにしてしまう。いくら華奢とはいえ、人ひとりを軽々と抱き上げてしまうのには、脅威の一言だ。
そして、例に漏れず大慌てするのはお姫様だっこをされる昴治くん。もちろん、顔は真っ赤である。
「ちょっ、ま、待って! これって、あのっ! 俺、自分で歩けるからっ! ブルーッ!!」
「どうせ誰も起きてない…お前もそう言ったな」
「それはそうだけどっ、でもほら俺重いだろッ!? 腰、痛めるって!」
「余計な気遣いだな。余り騒ぐと、聴衆が集まるぞ。イヤなら黙っていろ」
ぐっ、と昴治は言葉に詰まった。
確かに、このまま騒ぎ立てれば眠りについている子ども達のうち、何人かは起き出してしまうだろうから。
途端に大人しくなった獲物に満足して、蒼き獣は颯爽と風を切った。
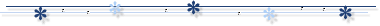
運んでもらい、医務室で手当までしてもらって、昴治は恐縮しきっていた。
右足に手際よく包帯をまいてゆく王者は、とても自分より一つ年下とは思えない貫禄がある。人の上に立つべき人間が所有する、絶対的なカリスマが存在しているのだ。
「きつくはないか」
「うん…、ありがとう、ブルー。ごめんな、用事あったんだろ」
「大した事じゃない、気に病むな」
「…なんかさ、ブルーって優しいよな」
途端、何とも表現しがたい表情で見上げてくる孤高の少年に、昴治は小首を傾げた。
「? どうかした?」
「そういう事を言ったのは、お前が初めてだ…」
「そう?」
不思議そうな様子の昴治だが、そんな少年の思考回路の方がよっぽど奇妙だとブルーは密かに嘆息した。
優しい、などと。
何の価値もない、それどころか、邪魔にしかならない余計な感傷をうみだす性質の悪い感情だ。言われたこともなければ、必要だと感じたこともないそれ。
「それに、そういうのはお前のことを言うのだろう……」
本心から出た言葉だったが、昴治は少し意外そうに目を見開くと、表情を翳らせた。
「俺は…、優しくなんかないよ。臆病なだけだ」
「………」
「ただ怖いだけなんだ。何もかもが」
「……恐れることは悪いことではない」
「?」
ブルーの言葉の意味を捉えられずに、茶金色の髪をした少年は困った風にしてみせた。
「恐怖を知らぬ人間は、ただのバカだ。どこの誰とは言わんがな」
祐希のことを言われていると察して、苦笑して見せる昴治だ。
「…ごめん、あいつまだブルーに喧嘩売ってるんだ」
「考えなしの向こう見ずで、無鉄砲。とてもお前の弟とは思えんな」
散々な言われように、乾いた笑いしか出てこないお兄ちゃんである。どれも的を得ているので、どうしてフォローしたものやら。
「あー…、と。でも、昔は俺のほうが、あんな風だったんだぜ。逆に、祐希は大人しかったな……」
「………お前がか?」
どうにも得心いきがたく、微かに眉根を寄せる表情がなんだかとっても可笑しかった。
「全然見えないだろ? すっごいイタズラ坊主でさ、嫌がる祐希を無理やりひぱって近所でも有名な頑固じぃさんの大切にしてる盆栽盗み出したりとか、そういう度胸試しに連れ出したりして。
今じゃ自分でも信じられないよ、もしかしたら祐希の性格の責任って俺にあるのかもな」
初めのうちはクスクスと軽やかに微笑みながら、後の方になっては真面目に考え込む様子で昴治は言う。
と、ふと気がつくとブルーがクックッと低く喉を鳴らせていた。
「な、何?」
滅多なことでは表情を変えないブルーが、肩を震わせて笑っているのだという事実に面食らいながら昂冶は何がそんなに可笑しかったのかと不思議に思う。
「…『近所の頑固じじぃで度胸試し』か、……クッ…ハハ…」
ぽかんとする昂冶なのだが、数秒後、ある事実に気がついて顔を赤くした。
そう、おそらくは。
人の死など、日常茶飯事の裏の世界で心と体を削るようにして生きてきた、鈍く輝くナイフのような彼。
自分の、平穏たる社会と安穏とした人生におけるコドモの遊戯の範疇を脱しない度胸試しなど、なんと幼く感じられることか。
「な、なんだよ。そんなに笑ことないだろ!」
己の短慮を恥じ入りながらも、目元まで赤く染め上げる少年は少し責めるような口調でブルーに抗議する。
と、ふいにブルーは真剣な瞳で昂冶の手をとって己の胸元へ引き寄せた。
「お前の話が聞きたい…」
「………え?」
想像もつかぬ程、酷く優しい眼差しで射すくめられ、ドキリと大きく胸が打つのを自覚する昂冶。
「お前の、思い出……」
「って、え。俺・の……? で、でも俺の話なんて面白くともなんともないよ、本当に普通に生きてきたから……っ」
いきなりな申し出に戸惑いばかりを表にする少年へ、更にブルーは言葉を重ねた。
「……それでいい」
「って、言われても……」
つぶらな瞳を白黒させて慌てる少年は若き覇王の願いを受け止めきれずに、困惑するばかり。
「……昂冶…」
急かすように名前を呼ばれる、その響きが甘くて年の割に幼い容姿の少年は仄かに頬を染め、大きな眼(まなこ)を何度も瞬かせた。
蒼色が優しく滲んで、吸い込まれる錯覚すら覚える。
「うん…じゃ、町内行事でさ……」
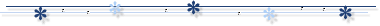
それからは、実にとりとめもないことを。
母の失敗料理の話や、町内会の肝試し大会。
学校で行われる行事や、果ては近所のスーパーの安売り日まで。
それらは、昂冶にとっては本当に日常の些細な出来事で。
しかし、真っ当な人生を歩まないブルーにしてみれば、どこれもこれもが珍しくあったのだった。
一通り話し終えて、そろそろ話題も尽きようかという頃になって、逆に昂冶はブルーへ彼の過去を強請(ねだ)った。
「…あのさ、俺はブルーの事が訊きたいな……」
「――俺の?」
「うん、ブルーの。どういう経過でリーベ・デルタに行こうと思ったとか、さ」
無邪気な質問に、ブルーは困惑気味に口を開いた。
「…それこそ、面白い理由じゃない」
影の落ちる横顔には、苦渋が満ちている。昂冶は、自分の考えなしの言葉がブルーを傷を抉ったのだろうか、と、己の迂闊さを後悔する。
「あ、あのさっ。あの…ブルーって喧嘩強いよなっ、負けないコツとかある?」
余りに、唐突なそれ。無理矢理話題を逸らせたことがみえみえだが、特に口を挟むこともせずに蒼の王者は、まぁな、と短く応えた。
「え? やっぱりあるんだ? へー…」
「興味があるのか?」
喧嘩のコツとやらにしきりに感心してみせる昂冶に、ブルーは問いかける。
「って。そりゃ、俺だって男なんだし、人並み程度には興味あるよ」
ブルーの声音が疑問に満ちていたことが多少引っかかったようだ。そんなに意外かなぁと思いつつ、頷いてみせる。
「…そうか」
「そうだよっ。だいたい、ブルーだって最初からそんな強くはなかったんだろ?
だったら俺も今から鍛えれば、多少は強くなれるかな?」
何もない廊下で一人でこけて、なおかつ足首を挫く。ある意味非常に器用な不器用人間と、カンの鋭い天才的な運動能力の持ち主の少年が同じだとは到底思いがたいが。
何故か、妙に張り切っているようなので、ひとまずそうっとしておくことにする。
「力を手に入れてどうする…?」
平和な日常で生きてきた、また、今の危機的状況を乗り越えたなら再び平穏な毎日を送るであろう少年に、過ぎた力は必要ないように思える。
「え…? うーん、どうするって言われても…。あるに越したことないだろ、強さってさ。もしもの時に、大切な人ひとり守れないようじゃ男として情けないしさ。
今なんか、自分の無力さを痛烈に感じてるよ」
こんなだしさ、と。
負傷した足首を指して苦笑する昂冶に、ブルーはぽつりと語る。
「守る、か…。
そうか、……余程、お前らしい答えだ」
大切なひとを守るため、そんな生っちょろい理由で強さを求め手に入れてきたわけではない少年には、寝言のような台詞だ。
生きるため。
単純明快な生存欲求に突き動かされて、生きてゆくためには、手に入れた力で自分以外の者から命すら奪ったこともある。
そう、生きてゆくために。
それ以上でも、それ以下でもない。
「…俺、今は誰かに守られてばかりだからさ…。
恩返しってわけじゃないけど、強くなりたいって切実に思うよ。地球に帰れたら、何か格闘技でも習おっかなぁ…」
「………お前がか?」
よっぽど意外そうに聞き返してくるブルーへ、昂冶はそんなに驚かなくても、と苦く思いつつ、そうだよ、と応えた。
「今からでも遅くないよな…。
強くなったら、ブルーだって護れるようになるかもしれないぜ、楽しみにしといてな?」
冗談めかして言う台詞に、ブルーは思いっきり前のめりの姿勢で肩を震わせる。笑いを堪えていることは明白で、流石にこの反応には男としてショックを受ける昂冶だ。
「な、なんだよ、そんなに可笑しいこと言ってないだろっ」
「ク、ククッ。…そうだな、楽しみにしてるか」
「……なんか、あてにしてないだろ。ブルー」
「いいや、そんなことはないが?」
蒼き王者は不敵な表情で飄々とし、昂冶の不満を受け流す。
暫く、納得いかないように頬を軽く膨らませていた少年は、ふと在ることを思いついて遠慮がちにブルーへ訊ねた。
「あのさ、ブルー」
「なんだ」
「え、っと。…ちょっと訊いてみたかったんだけど、銃持ってるだろ。ニードルガン。
それってさ、どうやって持ち込んだんだ? だって、リーベ・デルタで持ち物検査あっただろ」
純粋に『興味』から疑問を投げかけてくる純朴な少年へ、ブルーは口端を上げた。
「蛇の道は蛇…だ」
「え?」
「どうとでもなる…、俺はそういう生き方をしてきたから」
「ふぅ…ん?」
中途半端に鼻を鳴らす昂冶は、いまいち理屈を解していないようである。
思い出すのは、己のこめかみに銃口を突きつけて立ちつくす蒼き王者の姿。それは、雄々しくもあり凛々しくもあり、刹那的でもあった。
何故。
あのとき、ブルーは自ら果てる途を選択したのだろうか。
鮮烈な光景が、目に焼き付いて離れない。
「…俺は、土星圏出身でな」
「え、そうなんだ?」
「治安の悪さは指折りの、リンゼシティスラム街がホームだ」
「スラム街…」
聞き慣れない単語に目を丸くする少年へ、ブルーは微かに苦笑を浮かべる。
「そこでは、弱者は淘汰される」
昂冶は静かにブルーの言葉に聞き入っている。滅多に、己自身の身の上を語ろうとしない相手が、珍しく饒舌なのだ。ここで余計な口出しは無粋というものだろう。
「……生き残るためには、力を手に入れるしかない…。
形はそれぞれだがな、群れて個となす奴らもいれば、既存の強者へ取り入る人間もいる。
体を売って安全を得る者もな」
危険と隣り合わせるようにして生きてきた少年の言葉は、平凡な日常に埋もれ過ごしてきた昂冶にとってとても縁遠いもので、想像もつかない事柄だ。
「その、『力』の一旦が、こういうろくでもない知識というわけだ」
ろくでもない、と。
己自身で嘲るブルーの裏社会で手に入れた知識とやらは、相当のものなのだろう。
「………」
なんと言って返したものかと、困惑気味にする昂冶へ、蒼き獣は皮肉めいた表情で低く呟いた。
「……つまらんことを訊かせたな」
ふるふる、と。
緩く左右に頭を振って、ブルーの言い草を否定する昂冶は、ぽつりと零した。
「…俺が、リーベ・デルタに進学を決めたのは……、別に宙行士を目指してたってわけじゃなくてさ。
いろんな事から、逃げてきたんだ。
家族とか、学校とか、社会とか、そういう俺の回りにあったモノ全部から。凄く、なんていうのかさ、面倒で。何もかも嫌気がさして。
とにかく、昔の俺を誰も知らないとこに行こうって、それだけ考えたら宙行士養成所リーベ・デルタに辿り着いたんだ」
まさか、こんな大変な目に遭うとは想像もしてなかったけどさ、と。おどけてみせる台詞が、何処か悲しい。
「いざ、リーベ・デルタに来てみれば弟はいるし幼なじみもいるしで。全然、地球(ホーム)に居た時と変わんなくて、それで苛ついたりとかしてさ。
すっごい、ガキだよな。…たとえ、誰も知らない場所へ行けたとしても、何も変わんないのにさ、何かが変わる、何かが変えられるって思ってた」
「………」
無音の空気に包まれて、静寂が降り積もる。
苦痛を伴う沈黙では無く、優しい温度を感じられる世界がそこには在った。
「……………回りを取り囲む色々な事から逃げ出してきたはずなのに。俺、今は凄くホームが懐かしいんだ。勝手だよな、…自分から逃げてきたくせに」
撚った足首を撫でながら、昂冶はぽつんと苦笑した。
「俺には縁のない話だな…」
言う、ブルーに。
昂冶は、そっか、と納得しかける。
「俺には、…懐かしむべき何もがない」
しかし、続く。
渇いた告白に、少年は固まった。
「お前のような人間に、話すことではないな……」
口を閉ざす蒼き覇王は、ゆっくりと回想を巡らせた。
はじめて人を殺したのは、八つの頃。
理由が何であったのかも定かではない、あの街で人の命は紙幣一枚よりも軽いのだから、いちいち覚えているならキリの無い事だ。
銃を手にしたのは、五つから。
人を殺して、使い道を急速に覚え込んで。
この年になるまでに、牙の扱いを十二分に熟知した。
そんな過去の出来事の中、一体何を懐かしみ郷愁を募らせるというのか。
行くも退くも連なる獄界なれば、ただ前へ進みゆくだけ。
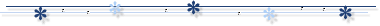
暫しの沈黙の後、ぽつりと昂冶は切り出した。
「…ブルーは、この先どうするつもりなんだ?」
「…………どういう意味だ」
「…えっと。この先さ、生き延びられたならどうするのかなぁって思って」
「……先、か」
「うん、俺はさ。こんな事なければ、普通に宙行士の免許とって、そのまま出来れば就職して…って、なんとなく考えてたんだけど。
こうなっちゃったら、免許所得とか言ってる場合じゃないだろ。養成所そのものもなくなっちゃったしさ。………どうするんだろ、って思って」
ぼんやりとしながら言う少年へ、ブルーは呆れたようなニュアンスを込めて返した。
「……今から、先の心配とはな。
明日の今をも知れぬ事態で、呑気なものだ」
「あははっ、そうかもな。
けど、――…どうせ未来はないって自棄になっちゃったら、それが本当になるかもしれない気しないか?
始めから諦めちゃえばいいのかもしれないけど、俺は…まだ生きたいよ」
願いを込めるように、昂冶は囁いた。
強く想う決意でもなく、確信でもって吐かれた台詞でもない。
ただ、ぼんやりと先を見据える姿は、何処か滑稽で何処かしっかりとした意思に満ちていた。
生きて、いたい。
「……考えてもない、未来(さき)のことなどな」
「ふーん? やりたいこととか、ないのか?」
「………お前は、どうだ」
「えっ、俺? うーん、とりあえず家に帰って…それから飯食べて寝たいかなぁ。後のことはわかんないな、けど、地球(ホーム)には帰りたいよ……」
今は、それだけが全ての願いなのだと。昂冶はほわんと微笑んだ。
「母星(ホーム)、か……。俺は還りたくもないがな……あの掃き溜めは気にいっているが、支配されるのは懲り懲りだ…」
何時になく饒舌にいる蒼き王者へ、昂冶はじゃあさ、となにげなく提案したのだ。
「地球に来ないか…?」
「…お前の母星に、か。退屈で死にそうな話だな」
くっ、と。再び喉を鳴らすのは、常に死と隣り合わせで命を磨いてきた少年だ。
笑われることを、昂冶とて見越していたのだろう。やっぱそうだよなぁ、と苦笑を零す。
「だが……」
「?」
ふいに、笑いの発作を収めて、ブルーは相手を絡め取るように見竦めた。
「……お前がいるなら…、それも悪くはない……」
「〜〜〜っ!?」
まるで手負いの獣に、それもとびきり綺麗な野生に懐かれるようだと、昴冶は顔を赤くした。
「あ、っ、あの…、ブルーっ?」
互いの吐息が感じられるほど、近く在る、海色の眼差しが酷く優しげで。
「……悪くはない…」
まるで、その蒼が宇宙の宝石・地球の彩(いろ)のようだ。
酷く懐かしくて、酷く儚い美しさで。
思わず伸ばした手を取られ、その手の甲へ口づけを。
穏やかな惑星、優しい生き物。
そんな場所でぬるま湯に浸かるような生き方も、余程、自分らしくはないが、悪くはない。
そう、思える程には、おそらく溺れている。
この感情の呼び方を――…今は、まだ知らない。