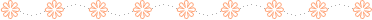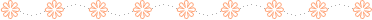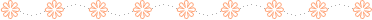#12
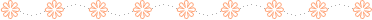
ヤバイ、かな。
うん、ヤバイかも。
血、出しすぎた。貧血気味かも。
左腕上がんないし。
ケータイで緊急信号は送っておいたから、このまま待っていれば。
きっと、絶対、香織が迎えに来てくれるだろうけど。
「ヒッ…」
鉄砲玉ってカンジの若い子だ。
きっと、組織に使い捨てのコマにされたんだろう。
――可哀想に、震えてる。
後頭部に銃口を押し付けられるなんて、きっと、初めてなんだろうな。
慣れたら、キモチ良くなるのにね。
「早目に口を割った方がキミの為だと思うけど」
ああ…何処か、遠雷が響く。
「俺は、別に――どっちでもいいんだよ?」
ゴリ、と少しだけ圧力を加えて、プレッシャーをかける。
「…ひ…ぅ」
ドォン、って。
鼓膜を打つ、酷い轟音。
続いて、滝のように一斉に落ちてくる雨粒。
正しく、豪雨だ。
こんな天気じゃ帰りはズブ濡れだなぁとか。
恒ちゃんは、ちゃんとお家に帰れたかなーとか。
思考は、取り留めも無い。
「――雨、凄いね」
「……?」
「こんなに降るんじゃ、傘持ってくればよかったな」
唐突な世間話に、鉄砲玉の子は、不審そうに俺を伺う。
無論、反撃の隙なんてあげないけどね。
「――俺にはね、大切な人がいるんだ」
銃口を構えた右腕はそのままに、俺は、愛おしむように記憶を辿る。
「だから、死んであげられない」
俺が消えたら、きっと、香織はとても悲しむから。
そっと、真っ直ぐ突き付けていた銃を、下ろす。
「キミも、もう――帰りなさい」
「……ッ、?」
俺の左腕を使い物にならなくした張本人は、突然の赦免に、一瞬呆けたようだった。
「真っ直ぐ帰るんだ。決して振り返っちゃいけないよ。
じゃないと、もう――戻れなくなるんだ。いいね?」
小さな子どもに言い聞かせるように、ゆっくりと、噛み砕いて。
――ああ、明日は晴れるといい。
俺は、雨の日が好きだけど。
香織が、青い空が気持ち良いと、笑ってくれるから。
――…ガウッ、ン…。
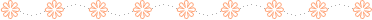
「…殺ったのか?」
廃墟ビルの足元の覚束無さなんて、なんのその。
威風堂々と仁王立ちで神出鬼没な魔性の美少年サマが現れる。
きっと、情報の流れは恒ちゃんから正宗君で、巧美ちゃんだな。
「――殺ろうと、思ったんだけどね」
「…珍しいな…」
「うーん、正規の暗殺者
じゃなかったし。なんか、香織の笑顔思い出したら駄目っぽくて」
へらっと返すと、素敵にイヤそーな顔されてしまった。
こんな時までノロケるな、この無自覚天然ド級M人間、なんて。
腹立たしそうに、アンプルを投げて寄越してくる。
「飲めよ。頓服だ。ちったマシだろ」
「薬、苦いからキラーイ」
「…――テメェ、マジで死ね」
コメカミをヒクつかせて吐き棄てる巧美ちゃんに、こわーい、と軽口を叩いて。
右の掌の上で薬を転がして、ふ、と溜息を吐いた。
「――ンだよ。ホントに飲まねーのか?」
眉を寄せて、不機嫌そうに訊いてくる巧美ちゃんに、ん、と小さく頷いた。
「俺、薬全般駄目なんだよねー。ヘタに飲むと、死んじゃうんだ」
「………死ぬ?」
「体質。まァ代わりに、痛覚も他人より鈍く出来てるから、ヘーキだよ」
「……ムカつく」
「あははー、ゴメンねぇ」
巧美ちゃんの、こういうストレートなトコ、恒ちゃんと似てる。
なんだかんだ言っても、やっぱり兄弟なんだなって感心してしまう。
「ンだけ無駄口叩けンなら、自力で歩けるだろ。外に車を待たせてる。オズんトコまで送ってやるよ。ついて来い」
「えー、香織が迎えに来るまで待ってるー」
「……気絶させられてーか? アァ?」
超絶爽やかな笑顔を手向けられて、大慌てで首を横にした。
「…ゴメンナサイ。」
ついでに、感覚の残っている右手を上げて。半端な降参のポーズを披露してみせた。
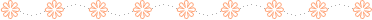
なんというか、メラっちは、真性Mでもういいやと思ったり(マテ
とりあえず、巧美サマがサイコーです
そして、多情で淡白なメラっちに萌えです
全て、自己完結、脳内設定な辺りが凄いデスネ☆
それでは、ブラウザは閉じておもどりくださいネ