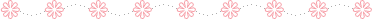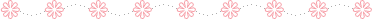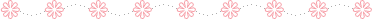#36
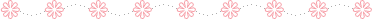
ボディガード・テスト第二段に見事おっこちた俺は。
ごろりと、ソファの上に不貞腐れていた。
大体、兄さんを『護る』っていうのが、そもそも無理難題だ。
逆立ちして鼻からピーナッツを食べるようなものだ。
「おいコラ、恒。ンだ、そのヤル気の無さは。あぁ?」
「だって〜……」
いつもなら、張り切って窓ガラスを磨いているけれど。
今日は、全然気乗りしない。
もうなんか、さっきので使い果たした感じなんだよね。
「まー、まー。テストも終わって疲れてるんだよ。
そんなにイジメないの」
兄さんにいびられる俺を優しくフォローしてくれるのは、米良さんだ。
銀色の髪に、蒼白な膚、北欧の血筋を感じさせる上品で綺麗な顔立ち。
お世辞でもなんでもなく、掛け値なしにカッコイイ人だ。
「それにほら、こないだ話したぶつぶつたらこ人形・赤タラ君を持ってきてあるんだよー」
「おぉ! これが幻のぶつぶつたらこ人形か!!」
……ちょっと、かなり変わった嗜好の持ち主だけど。
世間一般とはナナメ45度位の角度で常識を逆走する兄さんとは趣味が合うらしい。
赤・タラ君と呼ばれた、なんとも表現し難い物体を抱え、兄さんがご満悦だ。
「そーだ。恒ちゃん」
「はい?」
ソファの上でへたれている俺に、米良さんが優しく声を掛けてくれる。
「もし、時間があるなら少し練習してみる?」
「――…? 何をですか?」
主語を欠いた台詞に、キョトンをしてしまう俺に。
米良さんは、悪戯っぽい微笑みで答えた。
「こ・れ」
懐から、何気ない動作で取り出されたソレに。
俺は、きょとんと目を丸くしてしまった。
――…だって、それは。
この平和ボケした日本では、滅多に目にしないものだったから。
「米良、悪ふざけが過ぎるぞ」
「えー、ふざけてなんかいないよぅ? 恒ちゃんだって自衛手段は必要だし。
扱いに慣れるに越した事は無いと思うんだけどな」
そう。
美国社長の護衛である二人――つまり、米良さんと香織さんなんだけど。
この二人や兄さんなんかが当然のように携帯している銃が、目の前に差し出されたんだ。
「えぇええええぇええッ。お、俺ッ、無理ですよ!!」
当然のように慌てる。声が裏返ってしまうのは大目に見て欲しい。
なんたって、本当に驚いたんだから。
「最初っから扱える子なんていないよー。
恒ちゃんだって、美国探偵事務所の一人なんだし、荒事に自衛手段を持たないと」
「…それは」
分かっている。
だから、俺なりにカラダを鍛えたりとか。
ケンカのコツを教わったりとかもしてるんだけど。
如何せん、相手が正宗さんだったり兄さんだったりするもんだから。
全く、成長している気がしなくて、密かな悩みなのも事実で。
「アラ。いーじゃない。折角なんだし経験しておけば? 恒ちゃん」
「そーだな。コイツはどーでもいいが、射撃訓練ってのは面白そうだ」
美羽さんと兄さんの言葉に背中を押されても、ウンとは言えなかった。
「で、…でも」
これは、人を殺す道具。
そう思うと、触れるのが怖い。
俺なんかが、気安く触っていいものじゃないと思う。
「よーっし。んじゃ、どーせ依頼もはいってこねぇし!
今日はこれから本社の地下訓練場まで皆で出掛けっぞー!!」
「おー!!!」
「えぇえ!? ちょ、ちょっと兄さん!!」
戸惑う俺なんかお構いなしに。
美国探偵事務所の面々プラス役二名は。
そのまま、オフィス街の方へと繰り出したのだった。
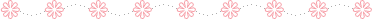
平日昼間の訓練場は、ほぼ貸切状態らしい。
夕刻から夜半にかけては自主訓練の人間が集まってくるとも言っていた。
いや、今はそんな事を思い出している場合じゃないんだけど。
「よく狙って。撃ち方の手順はもう覚えたよね?」
「ハ、ハイ」
こういうのって、手取り足取りっていうんだろうなって感心してしまう。
米良さんは、銃の持ち方から狙いをつける姿勢、発砲の手順、弾のチャージ方法。
そんな一つ一つを丁寧に教えてくれえて、今は、実施訓練中。
勿論、さっきから全部的から外れてばかりなんだけど。
「あ〜……、」
そして、やっぱり今度も外れ。
人型を模った的が目標なんだけど。
六発全部掠りもしないって…流石にちょっとへこむ。
「うーん、筋は悪くないんだけどね。
ショットの瞬間にカラダの重心がズレてしまうんだよね」
穏やかに微笑みながら米良さんが優しく慰めてくれるけど。
それにしたって、これだけ教わっておいてこの結果は、自分でも酷いと思う。
「おッ…前、ホントーに取柄がねェなァ」
「な、なんだよッ。そういう兄さんはどうなんだよ!」
休憩中の兄さんがチャチャを入れてくるのに、ムッときて言い返す。
すると、明らかに小馬鹿にした口調で肩を竦める兄さん。
「少なくとも、どこかのウン恒よりはマシだな」
「く…」
確かに、百発百ハズレだし、反論のしようも無いんだけど。
でも、悔しい。
絶対、的に当たるようになってやる。
「米良さんっ!!」
「んー? どしたの、恒ちゃん」
「お手本見せてくれませんかッ!」
「えー、俺ので手本になるかなぁ」
必死の形相で頼み込むと、米良さんは困惑しながらも頷いてくれた。
「じゃ、よーく見ててね。
まず、両手でブレないように脇を締めながら銃を構えて照準を合わせる。
で、引き金を引くんだけど、其の時に重心がズレてしまうと的外れな方向に飛んでしまうから。
しっかりと地面に腰を落ち着けるのがポイントかなー」
丁寧に解説しながら、一発。
当然のように、それは的のド真ん中に命中して。
ああ、やっぱりプロは違うなぁって感動する。
「ただ、ドンパチやってる最中にこんな教本通りの撃ち方なんてやってらんないんで――…」
言うと、米良さんは左手に銃を構え、隻眼を微かに細めた。
元が美形だから、顔立ちから表情が消えると、凄味があるというか、妙に迫力がある。
そして――、
連続する銃声。
米良さんは反動をモノともせずに片手で命中させてゆく。
スラリと伸ばした背中のラインが綺麗で、一瞬見惚れてしまったのは秘密だ。
「うーん、やっぱりちょっと外しちゃうな〜」
「え。全部当たってるじゃないですか!」
思わず、ぱちぱちと拍手を送っていたら。
そんな意外な事を言われて、目を丸くしてしまった。
「一応、ね」
「一応って…」
米良さんの撃った弾は人型の的の中央に全部命中していて。
撃ち抜かれた場所にイビツな穴が開いていた。
これで一応って、どういう意味なんだろ。
寧ろ、凄腕だと思うんだけど。
「香織なら、全部初弾と同じ場所に命中させるね」
「! マジですかッ!?」
「まじだよー。見せてもらおっか?」
本当に本当なら、相当凄い。
初弾と同じ場所にって事は。
的に開く穴は一つだけって事、で。
ありえないと思ってしまうけど、本当なんだろう。
香織さんの射撃の腕前を見たことはないけど。
あの年で美国社長の身辺警護を任されるくらいなんだから。
「ねー、香織〜」
「米良? どうかしたのか」
肉弾戦主体の正宗さんに銃の扱いをレクチャーしていた香織さんは。
米良さんの、何処か甘えるような響きの呼びかけに応じてやってくる。
「久々に、香織の腕前を見たいなーって」
「…見世物じゃないんだが」
呆れたように応じて眉を顰める香織さん。
元々、控えめな性格だから、こういうのは苦手なのかもしれない。
「おー、いいじゃねーか。見せてみろよ」
お祭り好きな性格の兄さんが、早速聞きつけて囃し立てる。
「今日の目的は恒君の射撃訓練でしょう。
大道芸人扱いはお断りです」
やんわりだけど、キッパリと断る香織さん。
やっぱ、苦手なんだ。悪いことしたかも。
「そんなこと言わずに。その恒ちゃんが見たいって言ってるんだし。ね?」
「あ、あのッ。俺、別に迷惑なら…」
粘ってくれる米良さんに慌てて遠慮する。
嫌がっているのを無理強いするのは良くないし。
「そーだそーだ、ケチくせーぞ。香織」
後ろでぷーぷー文句をつける兄さんは兎も角。
なんだか、少し…香織さんの様子が。
あれ?
米良さんをじっと見つめて…、あれ?
な、なんだろう、この雰囲気。
「…分かりました。では、ピンポイント・シュートを。
俺のは自己流ですから、余り参考にならないでしょうが…」
言うなり、香織さんは懐の銃を二丁――両手に構える。
その凛々しい姿に、ドキリとした。
俺とさして変わらない…寧ろ、小さなカラダで。
『奪う』道具を扱う。
酷く綺麗で、けれど何処か物悲しい。
「…耳、塞いでいてくださいね」
凄まじい銃声の後、左右二つの人型に。
一つだけ丸い穴が残されて。
香織さんの周囲には、十二発分の薬莢。
「おー、すげーじゃねーか」
「お見事だわー」
「流石、美国社長付きだねー」
「大した事ではありません。訓練と経験次第で誰にでも可能ですよ」
神技の披露に。
やんややんやと沸き立つ周囲を他所に。
「…米良さん…?」
「ん? どーかした? 恒ちゃん」
一瞬だけ、嬉しそうな困ったような顔をした米良さんの様子が。
とても印象的だった。
結局その日、俺は的に一発も当てる事が出来ずに終わってしまったのだけど。
後日、ちゃんと訓練に身を入れておけばよかったと。
後悔するのは、また別の話だ。
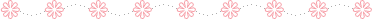
香織は無意識に嫉妬するタイプ
メラっちは、自覚のあるヤキモチをするタイプ。
でもって、かおりんは、自分の嫉妬心を嫌うし。
メラっちは、ヤキモチ焼かれるのも焼くのもどーんとこい。
そんなすれ違い・愛。