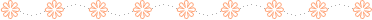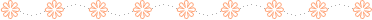#72
※米良がオズせんせーとイチャコラしてます、ご注意下さい
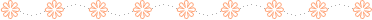
「……っ、 ん 」
「口の中は熱いね。体温低いのに」
「…ホンキチューするとは予想外。
それに、意外にテクニシャンだね。センセ?
ちょっと見直したかも」>
「おや、恋人的に惚れ直したと言って貰いたいところだね」
「あはは、じゃあ訂正。
惚れ直しちゃった…、セン、っ…」
ぐ、と顎を掴まれて。
もう一度、深く互いを貪るような激しいキス。
「ふ、……は、ぁ」
女子高生のコドモに見せつけるには度を越している気も。
けれど、相当アレな相手らしいので。
これ位過激で丁度いいのかもしれない。
そう自分を納得させて。
此方からも、仕掛ける。
何せ、今の"俺"はオズセンセの恋人だし。
それに、何より、背徳的な裏切りに耽る度に。
背中に突き刺さる視線が、快くてヘンになりそう。
「今日、いっぱいセンセとキスしちゃったなぁ…」
ようやく解放された口唇で、快楽の余韻を味わいながら囁けば。
恋人同士なんだから、当然だろう?
なんて、興の乗ったお言葉が。
「でも、センセも災難だね。
ストーカー紛いの女の子に付き纏われるなんて」
「そうだね、折角ならドロシーたんみたいなさー。
やわらかぷに幼女に追っかけ回されたい…」
「オズセンセ、よだれ、ヨダレ」
「おっと、失礼。僕とした事が」
ジャケットの内側から取りだしたハンカチで口元を拭って。
キスの為に外していた眼鏡を掛け直すと。
さて、お次はどうしようかと、肩を抱かれた。
香織は外の人目があるところではイチャイチャしたがらないし。
なんだか新鮮で、ドキリとしてしまった。
センセ相手になんて、なんたる不覚。
腕を引かれて、埃っぽい路地裏を出る。
背後には、複数の人の気配。
巧美ちゃんが、ラミアちゃん? とか言う女の子を誘導している予定で。
今のキスシーンも目撃されているはず。
普段ちゃらんぽらんにしているけど。
意外と、巧美ちゃん達は腕利きだったりする。
ケンカも強いしね。
「さぁて、お次は何処へ行こうか?」
昼時から待ち合わせて、今は、夕暮れの時間だった。
流石に男二人で映画館や遊園地も無いので。
オズセンセの希望に合わせて。
最新医療器具の展示会へ足を運んだ後。
軽い食事も兼ねて行きつけのショットバーへ。
そっち方面にも寛容なお店なので。
散々、センセとイチャイチャベタベタして見せた。
ケータイの時計が十七時を示す頃に店を出て。
そのままビルの谷間に入り込み。
大人のキスシーンをお披露目、と言うワケだ。
「センセはもう行きたい所は無いの?」
「うーん、僕は特にはないね。米良君は?」
「俺もオズセンセと行きたいトコは無いかなぁ」
「おや、辛辣だね。恋人に対してつれないことだよ」
「あはは、なら、恋人らしくヤルことやっとく?」
「そうだねぇ…」
あからさまなホテルのお誘いに、いやでも、と迷うオズセンセ。
「食事をしてからにしようか。
この近くに美味しい店を知ってるんだよ」
「へー、何のお店?」
「ベトナム料理だよ」
「…うーん。意外なような、しっくりくるような」
フレンチとか中華とか。
デートコースの定番料理に行かない辺り、先生らしいけど。
「ドロシーちゃんも大絶賛のお店なんだよ。
でも、混んでいる事が多くてね。
ちょっと電話で席を取れるか訊いてみるから。
米良君はここにいなさいね」
「はいはーい」
別に、ここで電話してもいいのに、とも思うけど。
確かに、道路沿いは色々な雑音を拾ってしまう。
ポッケからケータイを取りだしつつ。
オズセンセは適当なビルの外階段へ消えた。
ひとり、取り残されて手持無沙汰だ。
直ぐに戻って来るだろうけど。
「…あの ……」
「?」
と、不意に死角の右側から届く、か細い声。
「はい?」
何だろうと思ってカラダの向きを直すと。
そこには。
ロングストレートの黒髪、紺色のレース編ワンピースの少女。
丁度、高校生位の年頃で、見た目の特徴も一致。
おそらく、オズセンセのストーカーとかいう子なんだろう。
思い当って、ちょっと気を引き締める。
ベタに、 『この泥棒ネコ!』 とか言ってくるのかな、なんて。
ちょっと、構えていたら。
「……あの、 私、その…… うっ……」
「え、わ、ど、どしたの?」
泣かれてしまった。
ちょっと予想外で、わたわたとハンカチを探し――…、
「…… 死んで。」
左、脇腹を抉られる感覚。
うわ、そうくるかー、と。
じわり、滲む汗と血の感触を自覚しながら、一歩、よろめいて。
「米良ッ!!!」
「テメェ、何してんだっ!!」
今や、ストーカーから殺人未遂のハンニンへ。
確実なステップアップを果たした少女の背後から、見慣れた人影が幾つも見えて。
ほ、と一安心。
少なくとも、これで死ぬ事は無いはず、なんて。
呑気に構えた途端、追撃の刃が茜色に乱反射する。
流石に、何度も刺されるのはゴメンなので。
ひょいと、身体を回転させて避ける。
ついでにナイフを取り上げて。
よいしょー、と、背中側へ腕を捻じり上げた。
女の子に乱暴はしたくないけれど、しょーがない。
「うわ、何があったんだい!?」
よーやく電話を終えて戻ってきたオズセンセが。
おっかなびっくり、目を丸くして駆け寄って来るのに。
へらりと、何時も通りの笑顔を浮かべて。
「ちょーっと、ね」
べたり、と血濡れた右手を振って見せた。
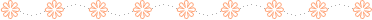
ラミアちゃんをヤンデレにして申し訳無い。
ちょっと変わってるけど、いい子だって分かってます。