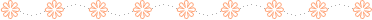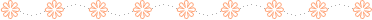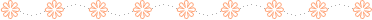#80
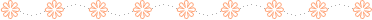
「へっ、黒先輩っ!?」
「往来で人の名前を叫ぶな、迷惑だ」
渋カッコイイ黒スーツの男性――黒さんが。
君人くんの背後で呆れ返っていた。
ちなみに、その右後ろには香織の姿。
かおりー、かおりー、と鳴きながら近付くと。
ふわり、優しく微笑まれて満足した。
一分一秒も離れたくないなんて。
現実感の無いワガママを言うつもりはないけれど。
やっぱり、出来るだけ一緒に居たいよね。
「…こんなところで話も何もねーだろ。
こっちだ。ついてこい、君人」
「……は、はい」
すごすご、飼い主に怒られたわんこみたいに。
耳をペタンと伏せながら、黒さんの言葉に従う君人くん。
基本的に、黒さんには弱いだなぁ、と感心。
まぁ、色々理由はあるんだろうけれど。
惚れた弱みってのが一番なんだろうなー、と。
「わ?」
ぼんやりしてたら、くしゃっと髪を撫でられた。
「香織?」
「行くぞ」
「え、俺たちも行くの?」
「面倒なのは分かるけどな。
放っておいて変にこじれたら、また巻き込まれるぞ」
「あー、それは確かに困るかも」
二人きりで話し合いをさせたほうがいいんじゃないかと。
そう思ったけれど、香織の言葉に納得。
確かに、最初の方だけでも、第三者がいた方がいい。
様子を見て、大丈夫そうなら出ていけばいいんだし。
後は、好きに乳繰り合ってくれればいいよね。
「…米良?」
「あ、うん。行くよー」
ふわふわの髪が可愛い、大切な俺のパートナー。
その手を繋ぎたくて、けれど人目があるから難しくて。
もっと大っぴらにイチャイチャしたいなぁ、なんて。
不可能な野望を胸に燻らせながら。
香織の背中を追った。
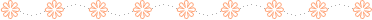
話の内容がかなりプライベートなので。
流石に、誰かに聞かれる可能性の高い屋外は論外。
結局、最初に俺達が休んでいたスタッフルームへ戻ってきた。
「………」
君人くんは、追い詰められたようなギリギリの表情で。
ずっと、押し黙って俯いていた。
ちょっと目元が潤んでいるのが可愛くて和む。
「あー」
口火を切ったのは、黒さんで。
ビク、と肩を揺らす顕著な反応に、バツが悪そうにする。
「…悪かった」
「……黒、先輩?」
びっくり、って感じで顔を上げる君人くん。
謝罪を口にした黒さんの頬はほんのり赤い。
決まり悪そうな仏頂面が妙に可愛らしい。
「アレにしこたま説教食らってな。
…で、腹を決めた。逃げっぱなしは良くねェしな」
「……決めたって…」
「ああ、保留になってた返事な。
ここでするわ。――前から答えは決まってたし、な」
「!」
ぴょん、と、ワンコが全身で跳ねた――気がした。
それくらい、激しい動揺。
当然と言えば当然だと思う、告白の、返事なんだから。
「…と、言うわけで。お前らどっか行け。シッシ」
「えー、いいじゃん。見物させてよぅ〜」
「米良。行くぞ」
わー、香織ったら強引〜。
がっしり腕を取られて、外へ連れ出される。
気になるんだけどなー、って駄々を捏ねてみたら。
ギロリ、睨まれて。
わざとらしく、首を竦めて怖がってみせる。
「ねーねー、香織〜?」
「何だ? デバガメなら認めんぞ」
「違うよぅー、じゃなくてさ。
黒さんをどーやって説得したのかなって思って」
スタッフルームの出口前で足を止めて。
凄く疑問に思っていた事を聞いてみた。
香織は他人のアレコレに口を出すのはあまり好きじゃ無くて。
人生の決断は、自身の意思で行われるべきだと言う考え方。
「…説得と言う程のものじゃないさ」
「そ? でも、黒さんって相当ガンコ者だよ?
どんな風に言ったのか興味あるなー」
「………。
本当に大した事は言って無いさ。
もし、俺が君人くんなら、生殺しは逆に辛いって伝えただけだ」
「うん?」
ちなみに、今更フォローを入れるのも何だけれど。
香織は年上であるはずの君人くんを。
『年下の後輩』のように扱ってる。
ちなみに、君人くんの強い希望によるもので。
見た目が二十歳くらいに見えるし。
実際に、後輩である事には変わりないので。
香織が本人の希望に添ってる感じだ。
「…体験談だからな、多少重みもあっただろ」
「体験談?」
「――…忘れてるとか言うなよ、散々人を焦らしておいて」
「………? あ、あー…。え、えへ?」
「……米良」
一瞬、本気で何の事が分からなくて。
むぅ、と首を傾げて考え込んでから、ハッとなった。
そういえば、俺も香織に告白された時、焦らしプレイだった。
「…お前は、本当に酷いな?」
「えー、こんなに香織の事が好きなのにー」
「だったら、サッサと返事をすれば良かっただろ。
半年も待たされたんだぞ!?」
「…だってさぁ、あの時って、…まだ香織十七歳だし。
コーコーセイだよぅ? やっぱり、こう、手を出すのが躊躇われない?」
「…そんな下らない理由で…」
「下らなくなんかないよ〜。
若い頃って一時の気の迷いとかもあるし。
引き返せない関係になってから、やっぱり間違えでしたとか…ね。
なったら、……困るだろうし。」
「俺は困らない」
呆れたような声、確信に満ちた言葉。
大好きな、大切な、俺の――狂おしい程に愛おしい、コイビト。
「…違うよ、困るのは俺。
大好きな香織に告白されて、幸せいっぱいの有頂天の天国から。
地面へ真っ逆さまとか、立ち直れそうにないもん」
「…そんなの、」
ぐい、肩を引き寄せられる。
耳元に香織の吐息を感じて、くすぐったい。
「……んっ、」
口唇を重ねられて、ぼうっとしてしまう。
優しい、キス。
慰めるような、慈しむような、愛しむような。
「…杞憂だっただろう?」
「……うん」
誰に見られるとも分からない、キス。
きっと、数秒、けれど凄く長く感じた。
「仕事に戻るぞ、香織」
「ん。けど、気ぐるみは置いてきちゃったよ?」
「あ――…、」
そっか、と困惑する様子が可愛い。
今このタイミングで部屋に戻るのは、流石に、馬に蹴られるだろうし。
「…ね、折角だし"休憩"しよっか?」
「う――…ん、そうだな。
結局、昼を摂れてないし…。ランチ休憩にするか」
あ、通じて無い。
まぁ、それはそれでいいけれど。
「うん。じゃー、いこっか。香織。
何か食べたいものある〜?」
「…特には無いが…、軽めの方がいいな」
時計は午後三時、スィーツな時間帯。
まるで誂えたかのような偶然。
オヤツの時間に、とびきりの甘いお菓子を独り占め、なんて。
本当に、まるで夢を見ているようだと。
じわり、広がる不安の波紋を。
幸せ、可愛い、大好き、
アイシテル。
不安の水面に欺瞞の小石を投げ込んで、心を誤魔化した。
"幸福"(いま)が決して永遠では無いと――…、
「かおり〜」
「うわっ!? なんだ、急に飛びつくな」
「えへへー、好きだよぅ〜」
「…知ってる」
「えー、俺もだ、とか言ってよー」
「…っ、こんなとこで言えるかっ!」
照れた香織に、ぽかり、軽く小突かれて。
暖かい背中から、べりっ、と引き剥がされてしまう。
残念。
くすくすと微笑う俺を、肩越しに睨みつける視線すら甘くて。
ずっと、こんな時間が続けばいいのになんて。
莫迦なことを、考えてしまった。
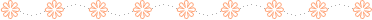
悲しくは無い、知っているから。
寂しくは無い、理解ってるから。
ねぇ、香織、俺は――…、