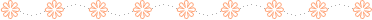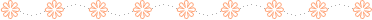#81
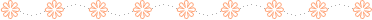
「なぁ、お前と香織って付き合ってるんだろ?」
部屋に押し掛けて、ソファの上でうんうん唸っていたかと思えば。
実に神妙な顔つきで、そう訊ねてきたのは、社長の親戚の男の子だ。
小学生ながら、放任主義の親の影響か、その子の発言や思考は何処か大人びている。
他人を困らせるような悪戯を仕掛けては、故意に周囲を掻き回して。
後から自己嫌悪に陥っては、どっぷりと後悔するような。
そんな一風変わった子ども、なのだが。
「そだよー? なになに、誰に聞いたの?」
スーツにブラシを掛けながら、受け流す。
別に動揺するような事でも無い――俺にとっては、だけど。
ちなみに、香織は台所でお昼を準備中。
「あのアホ探偵共だよ。
――で、聞きたいことあるんだけど」
「うん?」
巧美ちゃんからかー、と。
納得していたところに、上目遣いで窺ってくる、マサ坊にほんわかした。
我儘できかん坊で悪戯っこだけど、可愛いな、なんて。
「…その、こっ、こ、ここ、」
「コココ? ニワトリ?」
「違うっ!」
きょとん、と首を傾げると、がうっと赤い顔で反論された。
「その、こっ、く、……こく、」
ぎゅう、と自分の胸の辺りを拳で握り締める仕草に、張り詰めた緊張を感じ取る。
ブランド物の丸首ネックの長袖が、くしゃりと縮み、胸元の大きなリーフ柄が歪む。
「告白って、どーすんだっ!?」
ヤケクソ気味に叫ばれる、ガチャン、とお皿が落ちる音がした。
「かおりー?」
マサ坊の声に驚いてお皿を落としたみたいで。
大丈夫かなって心配して声を掛けると、慌てた様子で平気だと返された。
血の匂いが無いので、怪我もしていないだろう。
取りあえずは目の前のいっぱいいっぱいなお子様に向き合った。
「うーん、告白ねぇ…。ふふ、マー坊。若しかして…」
「うわっ、うわわわわっ、何も言うな!! 何も言うなよ!?」
「はいはい」
闇医者オズ先生の助手を務める幼い女の子ドロシーちゃん。
ふわふわカールのボリーミィな髪がとてもチャーミングな娘で。
実は、マサ坊はドロシーちゃんに一目惚れというやつ。
分かりやすい好意の態度から、恋心が筒抜けなのが微笑ましい。
「そうだね、やっぱり女の子はムードを大切にするからね」
手入れの終わったスーツをスツールに掛け直して、マサ坊の隣へ座った。
相談されている時は、正面に座るのは逆効果だとかなんとか。
中途半端な知識を頼りに、ちょっとした恋の助言者気取り。
「む、むーど?」
キョトン、と真っ直ぐな瞳で見上げられて、言葉に詰まってしまう。
そっか、男子小学生に『ムード』とか言ってもイマイチ伝わらないか。
「うーん、例えばだけどね。
星座が好きな女の子なら、夜空が綺麗な場所で告白するとか。
お花が好きな女の子なら、花束を用意してから告白するとか。
「…お、おう」
「でも、ドロシーちゃんは…。そうだねー、あの娘(こ)は大人だからね。
色々演出を凝らすよりも、直球勝負のがいいような気もするけどね」
「直球って…どうすりゃいいんだ?」
「そのまんま、体当たりって意味だよ。
二人きりになれるところに呼び出して、真剣に気持ちをぶつければ充分じゃないかな。
お金や権力なんかに誤魔化されるような価値観の娘じゃないからね。
でも…、そうだね。プレゼントのひとつくらいは用意してもいいかもね」
「…プ、プレゼントか。
でも俺、女がどんなもので喜ぶかわかんねーし…」
「以前も言ったと思うけどねー」
ぷに、膨れっ面のほっぺに人差し指を指しながら、偉そうに蘊蓄を垂れてみる。
「そういうのは、ひとそれぞれ、だからね。
どんな女の子でも喜ぶ万能な魔法のアイテムなんて存在しないよ」
「……うー」
「それに、マサ坊はまだ養われてる身なんだし。
高価な物を渡されても、大人なドロシーちゃんは困るんじゃないかな」
「……うぅぅぅ」
困ってる困ってる。
幼い恋に悩む姿は本当に微笑ましくて、ほんわかする。
全力で人生を生きている感じが愛おしくて堪らなくなる。
「んなこと言われても、どーしたらいいか…」
「ふふふ、そんなマサ坊にいい事を教えてあげようー」
「……?」
なんだよ、と不安そうに見上げる姿に加虐心が疼くのを自覚しながら。
やんわりと遣り過ごして、じゃじゃん、と目の前に広げたのは、色取り取りのビーズ。
「………は?」
面食らった声、どうすんだよ、と固まるマサ坊。
確かに、大の大人(男)がこんなものウキウキ広げたら、反応に困ると思う。
予想の範疇なので、気にせずに強引に話を進めた。
「ドロシーちゃんがいた孤児院で今度イベントがあるらしいんだ」
「…孤児院…?」
「あれ、知らない? ドロシーちゃん孤児院からセンセのところに引き取られたんだよ」
「……あいつ…、そっか。だから、」
「それでね、ひとりひとりお誕生会をひらく余裕が無いらしくてね。
年に一回、皆の誕生日を一斉にお祝いする会があるそうなんだけど。
そこで、ビーズで小物を手作りしてプレゼント交換しようって話があるそうなんだよ」
「…へぇ…」
「面白そうだから、俺も何か作ろうかと思って」
「…こういうの好きそうだよな、お前」
「えへへー」
「そんじゃ…、これで――?」
「うん。ドロシーちゃんは女の子なんだし、これで何か可愛い物を作ったらどうかな。
お手本の本もここにあるよー」
「……おう」
食い入るように手芸本のビーズ特集を眺めるマサ坊の頭を撫でて。
邪魔しないように、そーっとソファから退散する。
そして、キッチンへひょこりを頭をのぞかせて。
カレーを煮込むエプロン姿の香織に背中から抱き付いた。
「…米良。こら、邪魔だ」
「だいじょーぶだった?」
「? 何が、」
「お皿落としたでしょ? ヘーキ?」
「ああ、幸い皿も無事だ。
驚かせて悪かったな、米良」
「ふふっ、マサ坊があんなこと言い出すから吃驚しちゃったね」
「………」
「なんだか、アテラレルよねー。
真っ赤な顔して告白してきた何処かの子を思い出しちゃった」
「……めら」
苦々しい口調でカレーの火を止める香織に、ごろごろと懐く。
「ねー、香織ってさ、何時から俺の事好きだったの?」
「………」
「ねーねーねー」
「…答える必要性を感じないな、よってその質問は却下だ」
「けちー、教えてくれたら俺も答えるから。ね、ね?」
「………」
ぴくっ、って香織の肩が跳ねて、野菜を洗う手が止まった。
「………」
無言を貫いたまま、レタスをべりべりはいでいく。
葛藤中のようなので余計な横槍は入れずに大人しくしていると、ぷちとまとが唇に触れた。
「…後から、言う…から、お前も教えろよ」
「……ん」
パクリ、艶やかな表面を舐めるようにして赤い実を口で受け取って。
もぐもぐ、甘酸っぱい味と瑞々しい食感に上機嫌になりながら、小さく了承を返した。
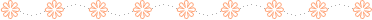
◆◆◆おまけ◆◆◆
「……おい、イチャつくなら俺が帰ってからにしろよ。このバカップル」
「!!」
「えー、いいじゃん。そこは空気を読んでみない振りしてよぅ」
「ほっといたら、いきなりおっぱじめるって、アホ探偵から聞いてんだよ」
「すっ、するわけないでしょう!!?」
「…どーだか。取りあえず、サッサとメシー。
それと米良、これちょっと分かんねーとこあるから、教えて」
「俺もそんなに詳しくないから…分かるかなぁ…」
「SEXよりは簡単だろ」
「えー、SEXの方が簡単だよぅ。ね、香織?」
「〜〜〜っ、知るかっ!! 馬鹿!!!」
◆◆◆おわり◆◆◆