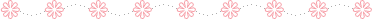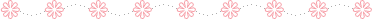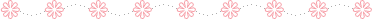#84
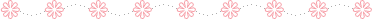
「た、ただいま…」
きぃ、と事務所のたてつけの悪い扉を開く。
俺の後ろには、普段、美国社長の護衛役を務める実力派なSPさんが二人。
はぁ、と溜息を吐いてしまう。
考え事をしながら道を歩いていたら。
普段は危険だから行かないように言いつけられてる。
ちょっと危険な地区へ入り込んでしまって。
帰り道も分からないし。
どうしよう、って困っていたとこに偶然出会った。
だから、事務所まで連れてきてもらえて、正直凄く助かった――んだけど。
なにせ――、
「遅かったな?」
「あー…、うん。ちょっと、うん」
ひょっこり、顔を覗かせた兄さんに微妙な返事をしてしまう。
マトモな男性モノの解禁シャツに黒のスラックス。
格好だけなら、以前の兄さんなんだけど。
どうにも、中身にはそう大差が無いように思えて。
扱いに、困る。
「ちあー、巧美ちゃん。おじゃましまーす」
「こんにちは、巧美さん」
手袋側の片手を挙げて、フレンドリーな挨拶の米良さんに。
ぺこり、礼儀正しい香織さん。
そんな二人に、当然、兄さんは不審そうに穿った視線を送った。
「…恒?」
「あ、えと。二人はこの事務所の出資者の美国社長の護衛なんだ。
此方は、米良さんと香織さん。失礼のないようにしてね」
「…ふぅん?」
「…と、言うわけですから。
お二人とも上がって下さい。どうせ、近いうちに報告しなきゃって思ってたんで。
ついでだし、説明しておきますね」
「……うん?」
俺と兄さんの遣り取りに首を傾げていた米良さんが、不思議そうに目を瞬かせて、頷いた。
「ま、いっか。
取り敢えず、おじゃましまーす」
「お邪魔致します」
細かい事に拘らない豪快――と言うか、暢気な性格の米良さんは。
促されるまま、何時も通りの気安さで香織さんと共に事務所に上がり込んだ。
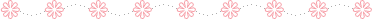
「はー、成程ねー。だから、巧美ちゃん、そんなカッコしてるんだねー」
事務所の中心に置いてあるソファにお互いに向き合う形で掛けて。
かくかく、しかじか。
これまでの経緯とこれからの事について説明して。
全てを聞き終えた、米良さんから出た言葉が、そんな台詞だった。
「あ? 別におかしかないだろ?」
「世間一般的にはおかしくないけど、巧美ちゃん的には、ね」
そう柔らかい苦笑を漏らす米良さんに。
意味が分からないと納得しない顔をする兄さん。
「そだ、巧美ちゃん。
ちょっとこれ試していい?」
「…?」
突然、良い事を思い付いたと言わんばかりに。
ちょっと得意気に、米良さんが懐をペタペタ触る。
そして――、
「じゃーん!!」
内ポケットから取り出した財布から。
タコ糸のついた五円玉を楽しそうに取り出してきた。
「…なんですか、それ??」
どうみても、何の変哲もない、ただの五円玉と糸の組み合わせだ。
「さいみんじゅつー! ってやつ」
「……はぁ」
「馬鹿か、お前」
「ちょっ、兄さんっ!?」
歯に衣着せないにも程がある。
余りの直球な物言いに、俺は慌てて兄さんの口を塞いだ。
基(モトイ)先生の催眠療法受けることになってるくせに、何て言い草だろう。
見た目は家出前の兄さんでも、中身は家出後に近いから困る。
「実はさー、スマート○ォンで催眠術コンテンツ無料で閲覧出来るんだけどね。
面白そうだから試してみたいんだけど、香織は全然ノッてくれないし。
ね、お願い。ちょっとやらせて?」
そう言いながら、今度は最新モデルのスマート○ォンを取り出す。
手慣れた操作で画面を開き、兄さんの返事を待たずに目的の情報を探す米良さん。
「…あー、分かった分かった。好きにしろ。
これ以上悪くなるこたねーだろ」
「えへへー、ありがとー、巧美ちゃん。
そうそう、折角だし、雰囲気出したいかな。
遮光カーテンを閉めてー、ろうそくとかないかな」
「非常用のがありますよ」
戸棚を探って未使用の太い蝋燭を取り出す。
倒れないように土台に細工してから、カーテンを閉め、準備完了。
「じゃー、五円玉を目で追ってね?」
言って、兄さんの目の前で米良さんは五円玉を振り子のように揺らす。
ゆらゆら、ゆらゆら、暗い室内をぼんやり浮かび上がらせる、不規則な橙の焔に踊る金色の円。
見るともなしに眺めていると、眠くなってくる――ので目を瞑った。
これじゃ、兄さんじゃなくて俺が催眠術に掛りそうだ。
そんな事を考えてたら、ぐらり、カラダが後ろに傾いた。
「へ?」
何が起きたのかと思って目を開けると、真正面に兄さんの顔。
只でさえ暗い室内で、背中からの炎が影を作り出して。
全く、表情が読み取る事が出来ない。
「……兄、 さん ……?」
態度はデカいけど、身体自体は小さくて華奢な兄さんが。
そのまま俺の腰の辺りに馬乗りになる。
所謂、マウントポジション、の状態。
ワケが分からなくて目を丸くしていると、
「え――…?」
どんどん、兄さんの顔が近付いて。
頬に添えられた冷たい手の平が、髪を撫でる感触に狼狽える。
「に……っ、 」
互いの呼吸が触れ合いそうな距離。
それでも、兄さんの顔は見えない。
何時もの悪ふざけだと。
取り返しのつかない事態になるまで、そう、思っていた。
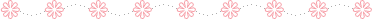
ちょっと進展したような、してないような
この兄弟はギリラインを綱渡りして欲しい気がします